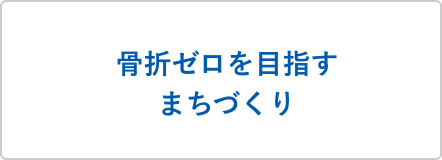諏訪赤十字病院は、冬期の御神渡り神事で知られる諏訪湖畔に建つ総合病院。2022年に開設100周年を迎え、永きにわたって諏訪地域の医療の中核を担ってきた。同院で血液内科を主宰するのが部長の内山倫宏氏だ。同科の診療方針の全ては、内山氏がただ1人で決める。なにしろ外来患者が月1000人を数える同科にあって、医師は内山氏しかいないからだ。「地域の市中病院でありながら、臨床試験の成果も治療成績も大学病院を凌ぐ」ことを信条とする内山氏の哲学に迫った。
施設情報
諏訪赤十字病院 血液内科
(長野県諏訪市)
1923年に開設された諏訪赤十字病院は、455床を有する地域の中核病院だ。
「血液がんの治療に手遅れということはありません」──。諏訪赤十字病院血液内科部長の内山倫宏氏は、患者の初診時にこう語りかけるという。
21世紀に入り、悪性リンパ腫、白血病、骨髄腫などの造血器腫瘍には矢継ぎ早に新たな治療薬が登場した。殺細胞型の抗がん剤もあるが、主流はドライバー遺伝子変異を標的とする分子標的治療薬だ。そのため、患者によって異なる遺伝子変異に応じた治療薬を処方することが、血液内科医の主要業務となっている。しかし、それは医師の役割の一部にすぎないと内山氏は言う。
患者を安心させることが治療の入り口
「重要なのは、不安にかられた患者を安心させることです。そのためには、徹底的に患者の視点に立って考える必要があります。通院は患者にとって大きな負担となりますが、帰宅の際には笑顔で帰ってもらうことが大切です」と内山氏は語る。
最新鋭の治療は大学病院で実施されるというのが日本の医療のいわば常識だが、それがそのまま患者の長期延命を約束するわけではないと内山氏は考えている。「患者の視点に立たなければ、どんなに進んだ治療であっても、患者の延命に貢献することはできません。まずは患者を安心させること。そのため最初に、治療方針をきちんと説明します。そして、悪性リンパ腫であっても、治療が遅れていたとしても、治療成績が損なわれるわけではないことを説明します」。
不安な表情で訪れた患者も、内山氏の話を聞いて表情がみちがえるように明るくなる。それが諏訪赤十字病院における造血器腫瘍の治療開始の合図でもある。
「大学病院への憧れを捨てよ」
内山氏が掲げる治療原則の1つに「治療を決して諦めない」がある。同病院で長期に治療を受けている患者の中には、大学病院で治癒を諦めるようにと言われ、終末期医療を勧められた患者もいる。一般に高齢患者は治療への忍容性が低く、患者の不利益につながるという観点から、積極的な治療が手控えられることが少なくない。
だが、こうした通念に内山氏は猛然と反論する。「『歳だから仕方ない』という言葉が、私は最も嫌いです。年齢に関係なく患者の体力に合わせた治療を行うことは可能であり、実際この病院ではそうした医療が可能になっています」。
その1例が発熱への対応だ。発熱患者に対して、すぐに対応することができる。迅速できめ細かい対応は、市中病院ならではの強みだという。内山氏の言葉の端々からは「大学病院、何するものぞ」という強い自負と気概がのぞく。優秀な人材をそろえる大学病院であっても、セクショナリズムや大組織ゆえの事情から、患者一人ひとりの事情を鑑みた細かな治療ができるとは限らない。そうした治療が必要となれば、市中病院こそがその任にふさわしいというが内山氏の信念だ。
「多発性骨髄腫の治療成績は、恐らく当院が日本でもトップクラスでしょう。市中病院が大学病院に劣るということはありません。WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の米国代表との一戦を前に、大谷翔平選手が日本チームの面々に『(有名大リーガーへの)あこがれを捨ててください』と檄を飛ばしたと報じられたのを聞いて、私と大谷選手の思いは同じだと1人感動しました」
 「市中病院が大学病院に劣ることはない」と力説する内山氏。
「市中病院が大学病院に劣ることはない」と力説する内山氏。
治療はエビデンスを最も重視して行う必要がある。それは当然だが、「エビデンスにこだわるあまり、患者一人ひとりの置かれた状況と乖離することがあっては、期待した治療成果を得ることはできません。EBMを逸脱するのは論外としても、患者の実態にそぐわないプロトコールを遵守する杓子定規な医療は、かえって治療を阻害することになってしまいます」と内山氏は言う。
例えば、悪性リンパ腫の標準治療レジメンの1つであるR-CHOP療法では、最初にリツキシマブを投与することになっている。しかし、一刻も早く容態を改善させる必要があると判断した患者には、治療の本丸であるCHOP療法を優先することもある。MRSA感染が認められた患者にバンコマイシンを投与する際には、最初の日に多くを投与し、血中濃度を早く引き上げることを目指す。「エビデンスから逸脱するわけでありませんが、エビデンスの本質を見極めて、状況に応じて柔軟に対応することが大事です」と内山氏は強調する。
また、菌培養のための採血では、2本の注射器を使って別々に採血する「2セット採血」が推奨されている。コンタミネーション(混入菌)のリスクを減らすためだが、これについても内山氏は、患者の侵襲性と、「措置の回数が増えればコンタミネーションのリスクが高まる」という考えから、1回の採血で多めの検体を確保する手法を採用している。「量が多ければ、感度も上がるのが道理です。この手法を採用してからというもの、私は菌血症を見逃したことがありません」と話す。
「Evidence+Experience」のEBM
EBMという言葉の「E」に、内山氏は「Evidence」とともに「Experience」を重ね合わせている。しかし、そもそもEBMは、医師個人の限られた経験を偏重する従来の医療を改める概念として提唱されてきた経緯がある。そこにExperienceを重ね合わせることは、EBMの後退を意味しないのだろうか。この疑問に対し「それは違う」と即座に否定した上で、内山氏は次のように語る。「私が行っていることは、エビデンスの本質を理解した上での改変であり、決してエビデンスを逸脱しているわけではないのです」。
一方で内山氏は、エビデンスの本質から外れて我流に陥らないように、意外な工夫も実践している。1つは、医師を相手にした講演を通じて、上記の改変の妥当性を確認することだ。自身の見解や実際に行った治療、その結果を積極的に講演で紹介することによって、聴衆の反応を慎重に観察する。このため内山氏は、講演を「自分の治療の標準化」と位置付けている。
もう1つは、国際的な治験への積極的な参加だ。最近は、再発性の多発性骨髄腫の標準治療を対照に、新薬の上乗せ効果を検証するためのグローバル第3相試験「IKEMA」に参加した。この試験では、新薬使用レジメンが無増悪生存期間を延長する結果となった(Moreau O, et al. Lancet. 2021 Jun 19; 397 (10292): 2361-2371.)。グローバル試験への症例登録は、国際的に認められた臨床医であることの証しでもある。
新型コロナ最盛期は病院に365日泊まり込み
高齢であっても、そして全身状態が悪化していても受け入れることを方針とする諏訪赤十字病院の同院血液内科では、外来患者が毎月1000人に上るという。それに加えて、入院患者も50人いる。先に紹介したように、内山氏はこれら全ての患者を1人で担当している。
造血幹細胞移植は近親者間でまれに行う程度ではあるが、それでもこれらの患者を1人で診ることは容易ではない。「実際、新型コロナウイルスが猖獗(しょうけつ)を極めた際には、365日にわたって病院に泊まり込みました」という猛烈ぶりだ。このように苛烈な働き方が展開される一方で、看護師の離職は少ない。その理由について、内山氏は「こんなに悪い状況の患者が治って退院していく」という驚きが、看護師を引きつけているからだという。内山氏の大車輪の活躍によって、血液内科の診療収入は院内でトップを維持し、しかも毎年増加しているという。
そんな内山氏には、自らの信条である「内山イズム」を広く普及させたいという野望がある。東京大学医科学研究所、静岡県立静岡がんセンターなどを経て、諏訪赤十字病院に着任したのが2009年。以来、まず院内で内山イズムにのっとった医療を確立し、それが完了すれば全国展開に着手する。そしてゆくゆくは、内山イズムを世界に広げていくという壮大なプランだ。「大事なことは、市中病院から積極的に情報を発信していくことです。当院が診察している患者数を知ると、その多さに驚く人が多いのですが、大学病院や大病院を振り向かせるには数で圧倒する必要があるのです」と内山氏は話す。
その一方で、いくら患者数が増えても、「患者の全てを負う」という診療方針を変えることはないとも語る。内山氏が自らのプラン通りに名声を得て、いつの日か諏訪を離れる日が来るのではないか、そんな心配する患者もいる。だが、患者の安心確保を信条とする内山氏は、そうした患者にこう語りかけているという。
「大丈夫ですよ。最高の治療を提供する私が、いつまでもあなたの隣にいますから」
---------------------------------
内山 倫宏(うちやま みちひろ)氏
1999年防衛医科大学卒、防衛医科大学病院にて臨床研修。東京大学医科学研究所、静岡県立静岡がんセンターなどを経て、2009年より諏訪赤十字病院血液内科勤務。2013年より同施設部長。2007年医学博士取得。日本血液学会認定血液専門医。