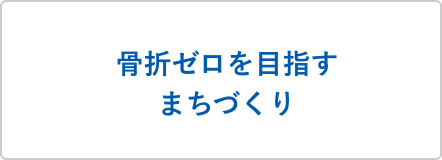聖マリアンナ医科大学のリウマチ・膠原病・アレルギー内科は小児期から高齢期まで、妊娠出産期や授乳期も含めて、ライフステージに応じた専門的な医療を届ける方針を掲げている。特に小児期と移行期の診療・医師教育に力を入れており、医局に所属する内科医と小児科医がチームを組んで病棟での診療に当たっている。全国的にもほぼ例がないこの特徴的な診療体制を作り上げたのは、2017年に主任教授に就任した川畑仁人氏だ。
施設情報
聖マリアンナ医科大学
リウマチ・膠原病・アレルギー内科
聖マリアンナ医科大学 リウマチ・膠原病・アレルギー内科
◎医局データ
教授:川畑 仁人氏
医局員:17人(常勤)
外来患者数:延べ約3万人、入院患者数:約600人
関連病院:2施設
聖マリアンナ医科大学のリウマチ・膠原病・アレルギー内科は1990年に難病治療センターの一部門としてスタートし、組織改編により1999年に独立した診療科・医局となった。現在、同診療科の常勤医師は17人で、トップを担うのは川畑仁人氏だ。2017年に第3代の主任教授に就任し、今年で7年目となる。
神奈川県内にはリウマチ・膠原病の診療科を持つ大学病院が4つある。同診療科がカバーする主なエリアは人口約150万人の川崎市を中心とする県の東北部だ。東京都世田谷区、狛江市、稲城市、町田市などからも患者が訪れ、年間の外来患者数は延べ3万人、入院患者数は600人を超えるという。診療規模の大きさが同診療科の特徴の1つとなっている。
「リウマチ・膠原病に関しては、様々なライフステージの患者さんが当診療科を受診されます。ですから小児科、産婦人科、整形外科など他の診療科とも連携して、成人の患者さんはもちろん、小児、高齢者、妊娠出産期、授乳期の患者さんにも、必要とされる専門的な医療を切れ目なく届ける体制を整えています。アレルギーに関しては、一般診療に加えて特殊外来の『遺伝性血管性浮腫外来』も開設し、これらの特徴を生かして医師教育や研究にも力を入れています」と川畑氏は話す。
小児リウマチ専門医の不足に危機感から新体制の医局を立ち上げ
生涯を通じた専門医療の提供を掲げる同診療科だが、中でも小児期と移行期のリウマチ・膠原病診療、および小児リウマチ医の教育に力を入れていることが、医局の体制から見て取れる。同医局には内科医であるリウマチ専門医10人と小児科専門医5人が同居しており、チームを組んでリウマチ・膠原病患者の診療に当たっている。全国的にもほぼ例がないこの特徴的な診療体制は、川畑氏が聖マリアンナ医科大学に着任する前、東京医科歯科大学で取り組んでいたプロジェクトに端を発するものだ。
東京医科歯科大学医学部には2016年に、寄付講座として「生涯免疫難病学講座」が設置された。川畑氏は同大医学部の膠原病・リウマチ内科講座准教授として、この新講座プロジェクトを担当していた。当時から抱いていた問題意識について、川畑氏は次のように話す。
「小児のリウマチ専門医が1人以上いる都道府県は、全体の半分程度です。その結果、リウマチ治療薬が大きく進歩したにもかかわらず、子どもたちにその恩恵を届けることが十分にできていないのです。小児科医が不在のため、成人を診るリウマチ内科医が、小児期や移行期の患者さんの診療を託されている地域もあります。そういったことも考え合わせ、小児期と移行期のリウマチ・膠原病を診られる小児科医、成人内科医を養成するために一定期間、その診療を深く学べる研修施設が必要だと考えました」
生涯免疫難病学講座の設置に当たり、寄付講座教授として外部から招かれたのが小児リウマチを専門とする小児科医の森雅亮氏(現・聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病・アレルギー内科教授=併任)だった。川畑氏は森氏とタッグを組んでプロジェクトに取り組んだ。
「2017年に、私は聖マリアンナ医科大学の主任教授に就任することになりました。そこで寄付講座を通じた取り組みをさらに発展させ、医局内に内科医と小児科医が同居し、より緊密に連携してリウマチ・膠原病の診療、教育、研究に取り組む仕組みを作ろうと考えたのです。森先生には当医局でも、小児科医のトップを務めていただくことになりました」と川畑氏は話す。
病棟では内科医も小児を診るし小児科医も成人を診る
聖マリアンナ医科大学のリウマチ・膠原病・アレルギー内科に所属する常勤5人の小児科専門医のうち、森氏を含む3人は既にリウマチ専門医を取得している。残り2人は、サブスペシャルティとして専門医の取得を目指しているところだ。小児科専門医の取得を目指し、同科に専攻医として在席している医師もいる。小児科専門医を取った後に、続いてリウマチ専門医を目指すとのことだ。
外来診療については基本的に、成人患者は内科医であるリウマチ専門医が、小児患者は小児科医が担当することになっている。一方、病棟については分担をせず、内科医と小児科医の混合チームで診療に当たっている。従って病棟では、内科医も小児患者を診るし、小児科医も成人の患者を診ることになる
成人内科医と小児科医が連携してチームで診療に当たることの、特に移行期診療における臨床的なメリットについて、川畑氏は次のように話す。「移行期には様々なライフイベントが起こってきます。端的なのは妊娠や出産ですが、成人特有の合併症なども徐々に出てきます。逆に、成人期にはほとんど見られない小児期の疾患が、移行期まで持ち越されることもあります。内科医と小児科医がそれぞれの知識と経験を基に、移行期の入口側の視点、出口側の視点を補いながら診療に当たることで、見落としなく適切な医療を提供することができると考えています」。
また、小児科医にも成人患者の診療を担当させることの教育面での狙いについて、川畑氏は「小児期や移行期のリウマチ・膠原病は成人に比べると症例数が少ないので、できるだけたくさんの症例を経験してもらいたい意図があります。壮年期〜高齢期の患者さんの診療を経験することは、病気の全体像を理解する上で間違いなく役立ちます。加えて小児科医は、小児期を診ていた患者さんから、移行期以降も診療を継続してほしいと希望されることが少なくありません。成人を診る能力を身に付けておけば、そういったケースにも対応が可能になります」と話す。
逆に内科医にとっても、小児リウマチの診療経験は、成人の診療に役立つと川畑氏は言う。「リウマチ内科医は若年成人から高齢者まで、普段から非常に幅広い年齢層の患者さんを診ていますが、病態は同じではありません。10代後半〜20代前半のリウマチ・膠原病は壮年期や高齢期とは大きく違っていて、むしろ小児期に近い点が多いのです。小児期や移行期の症例を経験することで、若年成人の病態への理解が深まるはずです」。
 聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病・アレルギー内科の医局メンバーたち。
聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病・アレルギー内科の医局メンバーたち。医局員を一括りにせず経験や事情に応じて業務分担
新しい診療・教育体制が軌道に乗るまでには、やはり苦労もあったようだ。リウマチ・膠原病・アレルギー内科で医局長を務める高桑由希子氏は「小児科医は特に大変だったと思います」と振り返る。
新体制の病棟診療は、主治医制ではなく、1人の患者を複数の医師で担当するチーム制を採っている。小児〜若年成人を中心に診るチームが1つと、若年成人〜高齢者を診るチームが2つあり、メンバーを一定期間ごとに入れ替えていくことで、小児科医も内科医も小児〜高齢者の診療を経験できる仕組みだ。
新体制のスタート後も、外来患者、入院患者ともに人数は成人患者の方が圧倒的に多かったため、全ての内科医がすぐに小児診療を手掛けたわけではないが、小児科医はみな最初から成人の診療も担当することになったという。「小児科医の中には成人診療をある程度経験したことがある人もそうでない人もいて、診療技術のレベル差が多少ありました。この課題をどう乗り越えるかが最初のヤマでした」と高桑氏は振り返る。
高桑氏が留意したのは「みなを一括りにしないこと」だった。まず、一人ひとりにこれまでの業務経験、何がどのくらいできるのか、医局に所属して何を学びたいのかなどを聴取。その情報を基に、それぞれの医師が無理なく、やりがいをもって仕事に取り組めるように初期のチーム配属や業務分担を決めたという。 その際、就業時間、就業日数、ルーティン業務などについて最低限のルールを決めて全体に不公平感が出ないように配慮した。「何とかうまくやれたのは、内科医は小児診療を勉強したい、小児科医は成人診療を勉強したいという探求心を互いが持っていたこと、そして互いを尊重し合い、みなで良い職場にしていこうという目標を共有できたからだと思います」(高桑氏)。

主任医長で医局長も務める高桑由希子氏。2005年聖マリアンナ医科大学卒の生え抜きだ。
新体制の一番のメリットは患者が受診しやすくなったこと
新体制になって一番良かったのは、患者が受診しやすくなったことだと高桑氏は言う。新体制前は、15歳前後の患者が来院した際に、「16歳より上ならリウマチ・膠原病・アレルギー内科、15歳以下は小児科」とやや杓子定規に振り分けていた。その結果、患者が本来受診すべき専門医の元にたどり着くのに時間がかかることがあったという。「新体制になって以降は、年齢に関係なくリウマチ・膠原病の患者さんは当診療科の医師がまず診察して、必要に応じて小児科など他の診療科とも連携する仕組みです。患者さんにとって、より受診しやすい仕組みになったと思います」(高桑氏)。
医師の教育・研修面でも、メリットがしっかり実感できているそうだ。「子どもに多い合併症、成人に多い合併症は違います。また、同じ合併症であっても、子どもでは特に気を付けなければいけないもの、高齢者で特に重症化しやすいものなど、年齢に応じて重要度が異なる合併症もあります。ステロイドや生物学的製剤などの使い方も、大人と子どもで異なります」と高桑氏は、年齢に応じた対応の難しさを語る。
その困難を解消するのが、小児科医と内科医のチーム制だ。「当医局では、両者が日々、病棟でのチーム診療を通じて助言し合い、互いに学ぶことができています。小児科医にとっては、小児〜成人の症例をたくさん診られること自体が良い経験になっています。リウマチ内科医にとっても、一般的な成人リウマチ・膠原病の診療をやってきた人は、小児のリウマチ・膠原病を診たことがほとんどないので、実際に症例を経験できる機会はとても貴重なのです」(高桑氏)。
小児科医にとっても内科医にとっても働きやすい職場を目指す
高桑氏は、今後の医局運営について次のように話す。「小児科医であれ内科医であれ、『こんな職場環境だったらもっとよりよく働けるのに』という思いが、10人医師がいたら10通りあると思います。昔と違って男性医師も育休を取って子育てに参加する時代ですから、自身の家庭の事情やキャリアについての悩みなどを気軽に相談できる医局を目指しています。私の友人には、出産後に仕事が続けられなくなり辞めてしまった医師がたくさんいます。それはすごくもったいないと思うので、当医局所属の医師の中からは、出産、子育て、介護などの事情で医局を辞めていく人が1人も出ないよう、これからも働きやすい職場づくりに取り組んでいきたいと思います」。
昨年の実績では、同医局の男性医師3人、女性医師1人が、出産・育児などで休暇を取ったり、時短勤務を利用したとのことだ。川畑氏は、「当医局には子どもを持つ男性・女性医師が多く働いています。医局長の高桑先生ご自身も3人のお子さんのお母さんであり、とても良いロールモデルになってくれています。私も働きやすい医局の環境づくりを全力でサポートしていきます」と話す。
医局の特徴を生かして臨床研究にも注力
今後の抱負について川畑氏は「臨床に関しては、小児から高齢者まで切れ目のない専門医療の提供を続けていきます。2018年に開設した『リウマチ・膠原病生涯治療センター』を核として、小児科や産婦人科、整形外科など関連の診療科と連携しているのですが、今後もさらに、患者さんにとってより受診しやすく、専門医療を受けやすい体制を進展させていきます。教育に関しては、内科医・小児科医それぞれが多くの症例を経験し互いに学び合う教育・研修の場となることを目指します。アレルギーについても、神奈川県下の中心的な施設として診療・教育の役割を担っていきます」と意気込む。
研究の面で川畑氏は、これまでT細胞の分化および機能に対するJAK(ヤヌスキヤーゼ)阻害薬の重要性などをテーマに基礎研究を続けてきた。その路線は継続しつつも、今後は臨床研究に力を入れていく考えだ。
「小児リウマチの生命予後は良くなってきたのですが、真のアウトカムは、成人期にどれだけ合併症なく、普段と変わりない日常生活を過ごせたかだと思います。小児期の治療が本当に正しかったのかどうかを知るには、成人期のアウトカムと小児期の診療を紐づけて検討する必要があると思うのです。小児〜成人の診療を切れ目なく担う当診療科であれば、そういったテーマを探求する臨床研究も可能です。他にはない診療体制や臨床規模の大きさといった特徴を生かして、リウマチ・膠原病の臨床研究でも医学に貢献していきたいと考えています」と川畑氏は話している。
--------------------------------------------------------------
川畑 仁人(かわはた・きみと)氏
1992年東京大学医学部卒業、同大学医学部付属病院内科研修。1993年東京都立墨東病院救命救急センター。1994年国立相模原病院内科。1996年九州大学生体防御医学研究所。1999年東京大学大学院医学系研究科博士課程卒業、同大学アレルギーリウマチ内科医員。2001年同科助教、2010年同科特任講師2012年同科講師。2014年東京医科歯科大学膠原病・リウマチ内科准教授。2017年より現職。