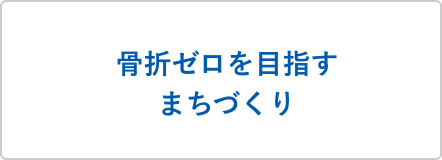福井大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科講師 の細川康二氏は2013年から2015年の2年半、ベルギーのブリュッセル自由大学(ULB)に留学していた。日本ではまれにしか実施されない大型動物を使った動物実験を学び、研究者として考え方の幅を広げることができたという。海外での生活を経て、自分自身や自分の国を客観的に見られるようになったこと、家族の絆が深まったことも、その後の人生において大きかったと振り返る。
先生プロフィール
福井大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科
細川 康二(ほそかわ・こうじ)氏
2003年 京都府立医科大学医学部医学科卒業、同年 京都府立医科大学附属病院 麻酔科研修医、綾部市立病院 麻酔科研修医。2009年 京都府立医科大学附属病院 集中治療部助教。2010年 京都府立与謝の海病院 麻酔科医長。2013年 Université Libre du Bruxelles大学院。2015年 厚生労働省医政局地域医療計画課 課長補佐。2016年 同課病院前医療対策専門官。2017年 広島大学大学院 救急集中治療医学/広島大学病院集中治療部 講師。2021年より現職。
――細川先生はベルギーに留学されていたのですね。どのような経緯で留学を決めたのでしょうか。
細川 留学は夢でした。いつかは海外で過ごし、研究に没頭する期間を持ちたいという気持ちがありました。しかし、現実には妻もいるし子どももいる。それから、仕事では様々な人とつながっていて、自分のわがままも言いづらい。そんな風に考え、なかなか一歩が踏み出せませんでした。
30歳代半ばを過ぎて、やはり「夢をかなえないまま40代になっていいのか」と自問し、歳をとるごとに留学は難しくなるだろうと考えて決断しました。
――実際に留学してみてどうでしたか。
細川 不安と期待が混じり合った海外での生活は、はじめは刺激的で、留学してよかったと思うことがいくつもありました。その一方で、実際に2年半暮らしてみると酸いも甘いも分かってくるというか、悪いところも見えてきますし、日本での生活とあまり変わらないと思う部分もありました。
大学院生として留学、大型動物を使った動物実験を手掛ける
――まず、留学先について簡単にご紹介いただけますか。
細川 私が留学していたのはベルギーの首都ブリュッセルにある、ブリュッセル自由大学エラスム病院のジャン-ルイ・ヴァンサン先生(Jean-Louis Vincent, Professor of Intensive Care Medicine, Université Libre du Bruxelles)のラボです。集中治療関係の先輩先生方の勧めで、同ラボへの留学を考えました。ヴァンサン先生は救急集中治療の領域で世界を牽引する人物です。
2013年当時、さまざまなガイドラインや数百本に上る研究論文の著者としてその名が知られていました。

総勢60人ほどの救急集中治療部のメンバー。中央最前列(やや右寄り)の男性がJean-Louis Vincent教授。(細川氏提供)
――留学先では「大学院生」の立場だったのですね。
細川 ヴァンサン先生から研究目的で長期滞在する場合、大学院生の身分となるよう言われました。
後から思うと、ベルギーのように多くの移民を抱える国では、国内に滞在する正当な理由と証明に好都合でした。リサーチ・フェローとして留学する人もいましたが、家族の滞在証明の発行手続きでトラブルが生じている例をいくつか見ました。
――留学先での研究内容について教えていただけますか。
細川 私がヴァンサン先生のラボで手掛けたのは、ヒツジの敗血症モデルを使った循環生理の実験です。
最初の半年は同僚の実験の補助をしながら実験手法を勉強しました。動物実験に携わる研究者には受講が必須である倫理や法律の講義を受け、試験にパスしました。
2年目以降は研究リーダーが企画した研究の実験プロトコルを担当し、そして自分で企画した研究の実験プロトコルも始めましたが終了を待たずに帰国しました。研究成果は帰国前に2つの論文としてまとめ、その後発刊されています。
 帰国前に記念の花瓶を手に、大型動物を使った動物実験を担当するメンバーとの記念撮影。(細川氏提供)
帰国前に記念の花瓶を手に、大型動物を使った動物実験を担当するメンバーとの記念撮影。(細川氏提供)――論文発表された研究成果以外にも、留学の成果と思っている点はありますか。
細川 研究の視点や考え方の幅を広げるうえで、留学経験は大変役立ちました。私の身近では小動物あるいは細胞を使った実験が大部分で、大型動物を使った実験がほとんど行われていません。しかし、前者の実験だけだと、得られた実験結果と臨床応用との隔たりが大きいです。大型動物を使った動物実験を短期間であれ経験してきたことで、小動物や細胞を使った基礎研究の結果を臨床に橋渡しする際に、どんな実験で何を確認すべきかといったことに、考えが及ぶようになりました。
的確で厳しかった査読ステップや研究発表、「Vague」と「So What?」で鍛えられた
――ヴァンサン先生からの「教え」で、現在も役立っていることはありますか。
細川 ヴァンサン先生の的確で厳しい査読や、研究発表・ディスカッションを経験したことは、現在も学生や若い医師の教育で役立っています。ラボでは研究者が論文原稿を書き、ヴァンサン先生に査読してもらっていました。先生から返ってきた原稿を見ると、いたるところにマーカーが引かれていて「Vague(not clear)」とコメントされていました。Vagueとは「曖昧」という意味ですが、不明瞭な部分を指摘しつつ、何が曖昧なのかは書いた本人に考えさせるのが先生のスタイルでした。
研究発表やディスカッションの場面で、ヴァンサン先生から「So What?」とよく言われたことを思いだします。「だから、どうなんだい?」といった意味ですが、この経験によって、さまざまな実験結果に対して「So What?」と常に自問するようになりました。つまり実際の患者への治療にどんな意味を持つのか、端的に答える必要性を強く意識づけさせられたと思います。簡単な誰にでも分かる言葉で人をより深く考えさせる。ヴァンサン先生は、教育者としても優れた人だったと思います。
ヴァンサン先生のようにはできませんが、私も今は学生や若い医師に対して、「ここの表現は曖昧なので、考え直そう」とか、「これがどういう風に患者管理に影響するのかしっかり考え直そう」といった指摘をするようにしています。
――冒頭で言われた「酸いも甘いも」についてですが、苦い経験もされたのですか。
細川 研究環境については、留学前に期待していたこととは違った部分もありました。ヴァンサン先生は研究の軸足が、動物実験よりも臨床研究に寄っていました。また、臨床研究ミーティングの基本言語がフランス語であったことも壁としてありました。研究者それぞれのラボでの悩み、人間関係の難しさなどは、日本でもベルギーでもあまり変わらないなと思いました。
海外留学を経て、強く優しくなることができた
――研究以外で、留学して良かったと思うことはどんな点ですか。
細川 いろんな国があり、いろんな人がいることを知って、日本という国や自分自身のことを相対的に捉えることができるようになりました。自分の外に視点を置いて、自分を客観的に見ることができるようになった、とでもいうのでしょうか。
その結果、自分が留学以前よりも強く、優しくなったと感じています。人と意見が違う場合でも怖がらず、どうすれば効率的に議論ができるか、話し合いで解決が可能になるかを冷静に考えられるようになりました。
それから家族の絆が深まったと感じます。ベルギーには私と妻、当時5歳の息子、2歳の娘の家族4人で渡航しました。家族の誰かがケガをしたり事故に遭ったりしても、日本にいるときは、私や妻の両親などに頼ることができました。しかし海外では頼れるのは家族だけです。家族みんなで力を合わせてトラブルを乗り切った経験が、家族の絆を強くしました。
――最後に、留学を考えている若い医師にアドバイスをお願いします。
細川 「行くしかないでしょう!」。留学前の私と同じように、「留学してみたい」という思いを抱えながらも踏み切れず、悶々としている医師がたくさんいるのではないでしょうか。人生は1回しかないのですから、チャンスを探して思い切って留学して、後のことは留学してから考えようくらいでいいと思います。
海外留学は冒険のようなものと思います。留学先で成果が得られるとは限りませんし、帰国後のポジションは保証されていない。楽しいこと、良いことばかりではありませんが、それでも行きたい気持ちがあるなら、冒険心を持って行ってみてほしいと思います。
会社組織と比べると、医療機関や大学など医師が所属する組織は、海外と協力して積極的に研究を進める取り組みがまだまだ遅れていると感じます。海外留学を経験した医師が増えて、組織的に海外との研究活動協力が行われる状況に変わって行くことを期待しています。
医局の紹介で留学、プレッシャーに打ち勝って研究を完遂
2021.11.15
米ハーバード大で下肢の研究に励み、休日にはアイスホッケーで現地の人たちと交流
佐藤 剛(さとう・ごう)氏
富良野協会病院(北海道富良野市) 整形外科 主任医長
2008年旭川医科大学医学部卒業、整形外科学講座入局。2008~2009年市立釧路総合病院(初期臨床研修)。2010年旭川医科大学病院。2011年市立稚内病院。2012年富良野協会病院。2013年北見赤十字病院。2014年旭川赤十字病院。2015年富良野協会病院。2016 ~2017年旭川医科大学病院。2018~2019年Massachusetts General Hospital, Foot and Ankle, Research and innovation Lab。2020年旭川医科大学病院。2021年より現職。