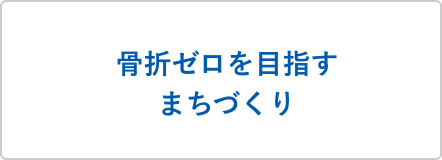北海道大学大学院医学研究院侵襲制御医学講座救急医学教室の和田剛志氏は、2016年4月からの約2年間、基礎研究を行うために米国のボストンに留学した。しかし、所属したボストン大学のラボではPI(主任研究者)との信頼関係を築けなかったことから、ハーバード大学のラボに移ることになった。異例ともいえる留学後のラボ移籍を乗り越え、外傷と免疫に関する新たな知見を得るなどの成果を上げて帰国した。
先生プロフィール
北海道大学大学院医学研究院 侵襲制御医学講座救急医学教室
和田 剛志(わだ・たけし)氏
北海道大学大学院医学研究院 侵襲制御医学講座救急医学教室 助教
2005年北海道大学医学部卒業。旭川赤十字病院、北海道大学病院での初期研修後、2007年北海道大学病院先進急性期医療センター救急科。2010年からの日本医科大学付属病院高度救命救急センター勤務などを経て、2013年北海道大学病院先進急性期医療センター救急科助教。2016〜2018年に米国のボストン大学とハーバード大学に留学。2018年に北海道大学病院に戻り2020年より現職。
──まず初めに、留学することになったきっかけを伺えますか。
和田 2005年に大学を卒業して以来ずっと臨床をやってきたので、以前から大学院などで基礎研究を手がけたいという思いがありました。ただ、日本にいると大学院生でも臨床を担当せざるを得ないので、せっかくなら研究に専念したいと考えたことが1つ。もう1つは、海外で生活してみたいというミーハーな気持ちからです(笑)。
ちょうどその頃、娘が4歳になっていました。日本にいると当直などで家を空けることが多いのですが、家族と過ごせる時間が一番楽しめる時期ではないかと考えました。また、娘が英語をしゃべれるようになってくれればいいな、という思いもありました。そういういろいろなタイミングが、卒後12年目となる2016年にやって来たということです。
──当初の留学先はボストン大学だったのですね。
和田 はい、2016年4月からボストンでの研究生活を始めました。北海道大学では代々DIC(播種性血管内凝固症候群)の研究を行っていたこともあり、以前より交流のあった、血液凝固に関する研究を手がけているボストン大学のラボに籍を置きました。臨床に近い分野でもあった凝固線溶の研究ができるということで、そこに留学することに決めたのです。
ところが実際に行ってみると、予想外の状況が待ち受けていました。思うように実験をさせてもらえなかったことなどから、ラボのPIとの信頼関係を築くことが困難になってしまったのです。そのために悶々と悩む日々が続き、留学先のラボを変えることを考え始めました。その矢先、妻の父が危篤状態に陥ってしまい、8月に日本に緊急帰国することになりました。
その際、留学のために骨を折ってくださった先生にご挨拶を兼ねて状況を説明したところ、「もし移る先があるなら移っていいぞ。先方には、いくらでも頭を下げるから」と言っていただけたのです。私としても、いろいろなことを犠牲にして留学をしている以上、無駄な時間を過ごせないという思いが強くなっていたので、この言葉を受けて移籍先探しを本格化させました。
──渡米直後の留学先の変更は、容易ではなかったと思います。どのように進めたのですか。
和田 ボストン在住の日本人医師の何人かに相談して、移籍の可能性を探りました。そのうちの1人である山川一馬先生(現・大阪医科薬科大学救急医学教室准教授)が、ご自身が去ることになったばかりのハーバード大学・ブリガム&ウイミンズ病院(Brigham and Women's Hospital / Harvard Medical School)のジム・レデラー先生(James A. Lederer, PhD)の研究室(Department of Surgery 〔Immunology〕)を紹介してくださいました。
北海道大学の先輩でもある山川先生がレデラー先生に話をつないでくださったおかげで、比較的スムーズに研究室の移籍が実現しました。山川先生も、留学中にラボを変更した経験をお持ちだったので、私の大変な状況を理解してくださいました。紹介を受けたレデラー先生も「それは大変だ」ということで、すぐに手続きを進めてくださいました。そうして2016年12月から2018年1月まで、レデラー先生のラボで研究生活を送ることになりました。
──和田先生は有給と無給、どちらの立場で留学されたのでしょうか。
和田 ボストン大学でもハーバード大学でも無給でした。ですから留学先の移籍に当たり、金銭面でもめることはありませんでした。ハーバード大学に移る際も、有給のポジションを要求していたら、スムーズな移籍は難しかったと思います。
米国では無給でしたが、私は北海道大学に席を残した形で行かせてもらったので、大学病院から基本給が支給されていました。また、出張扱いでもあったため、出張費という形で医局に相応の費用も負担してもらっていました。そういう面では恵まれていたと思います。
──晴れて移られたハーバード大学のレデラー研究室はいかがでしたか。
私たちは「ジム・ラボ」と呼んでいましたが、移籍前に比べたら天国のようなところで、本当に居心地の良いラボでした。「ジム・ラボ」には、アフリカ系やインド系を含むアメリカ人に加え、中国から来ていた人もいて、メンバーは多彩でした。また、PIのレデラー先生がとても良い人で、自室のドアをいつも開放して「困ったことがあったらいつでも訪ねてきなさい」とラボのメンバーのことを常に気にかけてくださり、些細なことも丁寧に指導してくださいました。
そんなレデラー先生がPIを務めるラボでしたから、雰囲気は非常にアットホームで和気あいあいとしていました。毎週金曜日のミーティングでは、ボストンで最もおいしいと言われる有名店のピザをほおばりながらディスカッションをしたり、夕方には先生から指令を受けてビールを買いに走り、乾杯してから家路につくようなこともよくありました。
またジム・ラボでは、仕事の後にYouTubeで日本のバラエティ番組を視て、みんなで大笑いするのも定番でした。私のラボ入りが決まった頃は『風雲!たけし城』がブームとなっており、私の名前の読みが「タケシ」であったことから、「あのタケシズ・キャッスルのタケシが来るのか!」とラボが騒然となったという笑い話も聞きました。
 ジム・ラボの飲み会で。ラボのメンバーは多彩だ。(和田氏提供)
ジム・ラボの飲み会で。ラボのメンバーは多彩だ。(和田氏提供)
──とても良い雰囲気のラボであることが伝わってくるお話ですね。ラボとしての活動実績はいかがでしたか。
和田 ジム・ラボの研究テーマは、外傷に伴う免疫の変化です。正直なところ、研究で実績を上げて多くの論文を世に送り出すことに注力している印象は、あまりありませんでした。むしろ論文を出すことに執着がないというか……。実際、私も留学を終える際に論文を書いて置いてきたのですが、3年以上たった今も日の目を見ていません。
レデラー先生は本当に実験が好きな方で、ベンチに座って「これはファンタスティックだ!」などとおっしゃりながら実験に取り組んでおられるのですが、そこから先に進まないんですね(笑)。聞くところによるとジム・ラボでは、留学時に書いた論文が世に出るまでに4〜5年かかる例も少なくないということでした。
これには、ラボ運営のための研究費獲得に汲々としなくて済むという、ジム・ラボ特有の事情が関係していていたようです。ジム・ラボでは、少量の検体で多項目の免疫学的評価を可能にする「CyTOF(Cytometry by time-of-flight:サイトフ)」という機器を早い段階で導入していたのですが、長年の経験を生かし、その試薬を独自に作成し他の研究室に販売することにより収益を得ていたので、ラボの運営費には困っていませんでした。そうした事情が、余裕のあるラボ運営につながっていたのだと思います。
──和田先生もCyTOFを用いた研究に取り組んでおられたのですか。
和田 はい。私は外傷と肺炎の関係を研究しており、肺炎球菌に感染させたマウスのうち、頭部外傷を負ったマウスと熱傷を負ったマウス、通常のマウスの3つそれぞれで、免疫がどのように変化するのかをCyTOFで解析しました。その結果、肺の細菌クリアランスを最も向上させ生存率が改善した頭部外傷のマウスにおいて、肺内で特異的に増加する好中球サブセットがあることを突き止め、同定することができました。
この成果は、追試が望ましいこともありまだ論文にはしていませんが、2017年と2018年のショック学会(Annual Conference on Shock)で発表したところ、2年連続で学会参加費の助成対象となるトラベルアワードを受賞しました。さらに2018年は前年より格上の、学会長の名を冠したトラベルアワードをいただきました。留学中の目に見える成果は、今のところこの2つということになります。
 2018年のショック学会でトラベルアワードを受賞して、レデラー先生(中)と同僚だった中堀泰賢先生(右、現・大阪急性期・総合医療センター救急診療科副部長)と記念撮影。(和田氏提供)
2018年のショック学会でトラベルアワードを受賞して、レデラー先生(中)と同僚だった中堀泰賢先生(右、現・大阪急性期・総合医療センター救急診療科副部長)と記念撮影。(和田氏提供)
──プライベート面についても伺います。ご家族はボストンでの生活を楽しんでいらっしゃいましたか。
和田 妻と4歳の娘と一緒に渡米したのですが、娘は日本で通っていた幼稚園が大好きだったので、当初は「行きたくない」とだいぶ泣きました。でも、実際には妻とともに半年くらいでペースをつかみ、当初の予想よりも早くなじんでくれました。大学卒業後、十数年ぶりの当直なし・土日休みの生活を送る中で、成長する娘と一緒に過ごした時間は、私にとってかけがえのない貴重なものとなりました。特に忘れられないのは、3泊4日で出かけた「ディズニークルーズ」です。フロリダ発の大型客船でカリブ海を一周するツアーだったのですが、夢のような時間を過ごしました。
また、私が留学していた2017年には、アメリカンフットボールリーグ(NFL)の頂上決戦であるスーパーボウルで、地元チームのニューイングランド・ペイトリオッツが大逆転劇の末に優勝するという出来事がありました。この時の街の盛り上がりは尋常ではなく、雪がちらつく寒空の下、ラボのメンバーたちと優勝パレードを見に行ったことも一生の思い出になりました。
 ニューイングランド・ペイトリオッツの優勝パレードでラボのメンバーたちと。(和田氏提供)
ニューイングランド・ペイトリオッツの優勝パレードでラボのメンバーたちと。(和田氏提供)
──最後に、留学を志す若い医師へのメッセージをお願いします。
和田 留学は実際のところ、行かないと分からないことが多いです。でも、行くと決めたら突き進むしかありません。先のことをあれこれ考えても行動できなくなるだけですから、取りあえずやってみて、駄目なら別の手を考えるというようにしていかないと前には進めません。本当に駄目だったら、日本に帰ってきてもいいわけですから。
私自身は、留学後に所属ラボの変更に追い込まれるなど辛いことも多かったですが、後悔はしていません。留学先には高い志を持った日本人医師も多くて刺激を受けましたし、今もコミュニケーションを取って一緒に研究活動に携わっている人もいます。そういう輪が広がったことも収穫でした。留学を考える若い医師には、あまり考え過ぎずに、行きたいんだったらとにかく進むしかないよ、と伝えたいですね。