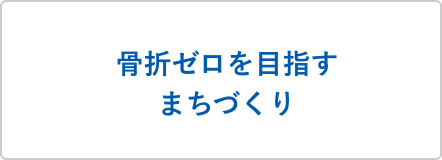京都府立医大の妹尾高宏氏は米国・ハーバード大学ボストン小児病院のラボに留学し、2021年3月に帰国した。3年8カ月の留学期間について、ディスカッション、コラボレーションに対する意識の高さがとても印象的だったと振り返る。新型コロナウイルス感染症の影響でラボは一時閉鎖を余儀なくされ、研究の進捗は大きく遅れた。しかしそのような状況でも、オンライン・コミュニケーションのノウハウなど、得るものがあったという。
先生プロフィール
京都府立医科大学大学院 医学研究科 免疫内科学
妹尾 高宏(せのお・たかひろ)氏
京都府立医科大学大学院 医学研究科 免疫内科学 病院助教
2002年京都府立医科大学卒、同大学内分泌免疫内科学教室入局。同大学附属病院内科、京都第二赤十字病院内科、京都第一赤十字病院呼吸器科を経て、2011年京都府立医科大学大学院医学研究科免疫内科学病院助教、2015年同大学大学院医学研究科免疫内科学助教。2017年7月から米国ハーバード大学ボストン小児病院に留学し、2021年に京都府立医科大学に復帰した。
――米国・ハーバード大学医学部の附属病院に留学されていたそうですね。
妹尾 小児科部門を担うボストン小児病院(Boston Children's Hospital)で、2017年7月から3年8カ月間、基礎研究を行ってきました。同病院は小児科の専門病院ですが、基礎研究のテーマは小児科に特化していません。私が所属していたのは外科学血管生物学分野のティモシー・ラー教授(Timothy Hla, PhD Professor、Vascular Biology Program, Harvard Medical School)のラボです。
――どういった経緯でその留学先を選んだのですか。
妹尾 私は大学院で自己免疫疾患の血管炎症をテーマに研究をしていたのですが、2016年頃にちょっと行き詰まりを感じていて、それを打開するために海外留学してみようかと考え始めていました。そんなとき、同じ医局の河野正孝先生(京都府立医科大学大学院医学研究科免疫内科学、医学部内科学教室内分泌・免疫内科学部門講師)から、ラー先生のラボで免疫が専門の研究者を探していると教えてもらったのです。河野先生は、ラー先生がハーバード大学に移籍する前コネチカット大学のラボに留学されていました。
ラー先生のラボの主な研究テーマは「血管」と「免疫」で、私の研究テーマにぴったりだったのです。これ以上のチャンスは無いと思い、河野先生に紹介してもらってラー先生に連絡を取りました。
渡米した時の私の年齢は40歳でした。医師が海外留学する年齢としてはやや遅いのですが、医局の人員も増えてきて、海外留学を考えられるようになったという事情もありました。
――ラー先生は日本の学会にもよく招待され、講演されている有名な方ですね。
妹尾 COX-2受容体、生理活性脂質であるスフィンゴシン-1-リン酸(S1P)受容体のクローニングに世界で初めて成功し、抗炎症薬の開発につなげたことでも知られる著名な研究者です。ラー先生のラボは、この分野では世界のトップラボの一つに数えられています。
私の主な研究テーマは、S1Pによる免疫制御のメカニズム解明でした。具体的にはS1Pが好中球やマクロファージをどのように制御しているのかを明らかにするのが目的で、世界でまだ誰も成し遂げていない内容でした。
この研究テーマとは別に、ラボの他の研究者と共同研究も複数行いました。ラボ内には、がん、痛み、感染症など、異なる専門を持つ研究者が10人ほどいました。それぞれが研究を進める中で、免疫細胞の制御やアレルギー疾患などに関してサポートが必要な場合に、私が共同研究者として入って手伝っていました。
 ティモシー・ラー教授の研究室の仲間たちと。中央がラー教授、右端が妹尾氏。(妹尾氏提供)
ティモシー・ラー教授の研究室の仲間たちと。中央がラー教授、右端が妹尾氏。(妹尾氏提供)
――研究成果はいかがでしたか。
妹尾 S1Pが好中球の機能を変えることを、世界で初めて実験的に証明することができました。好中球は体内で炎症を起こす原因と考えられてきましたが、「炎症を抑える」という逆の機能がS1Pの働きで促進されることを明らかにしました。現在、論文を投稿中です。これが一番大きな研究成果ですが、他にも2~3本の論文投稿を予定しています。
――振り返ってみて、ハーバード大学の研究環境の良さはどういったところでしたか。
妹尾 一流の研究者が身近にたくさんいて、本当の最先端を学べたことがまず一つ。ベンチャー企業を多数輩出しており、もちろん研究資金は潤沢でした。それから特に印象的だったのは、ディスカッションやコラボレーションの敷居がとても低いことです。研究者それぞれが自分の領域を囲い込むのではなく、互いにアイデアや知識を出し合って大きな成果を目指す意識が、大学の文化として根付いていました。話をしよう、ディスカッションしようというマインドがものすごく高いので、相手が著名な研究者であっても、電子メールでアポイントを取って2時間後には直接話をしているのが、ごく普通のことでした。
 ラー教授とのラボでのツーショット。(妹尾氏提供)
ラー教授とのラボでのツーショット。(妹尾氏提供)
新型コロナの影響で自由なディスカッションにも制限
――新型コロナウイルス感染症の影響は、ボストンではどうでしたか。
妹尾 2020年2月に、船内に多数の感染者を抱えたクルーズ船が横浜港に入り、日本で大騒ぎになった様子は米国でも報じられました。しかしそのときはまだ、米国では他人事のような雰囲気でした。その約1カ月後、ボストン市内で開催されたサイエンティフィック・ミーティングで新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、死者も出ました。それからはあっという間に街中に感染が広がって、マサチューセッツ州だけでも感染者が連日2000~3000人に上りました。一番ひどい時には1日に1万人を超えていました。
大学はほぼ全面的に閉鎖となり、新型コロナウイルス感染症以外の研究はすべてストップしました。2カ月弱のロックダウン期間中、私たちは基本的にラボに行くことができず、自宅で論文を読んだり、オンラインでラー先生やラボの仲間とミーティングをしたりするしかありませんでした。
街はゴーストタウンのようになり、病院は医療崩壊していました。人工呼吸器が全然足りなくて、1台を複数人につないでいるような状況でした。私は日本の臨床医だということで、「待機要員」として登録されましたが、結局、駆り出されることはありませんでした。
ロックダウンが解除されても、動物実験の再セットアップに何カ月もかかったり、必要な試薬がスムーズに入手できなかったりで、研究の進捗は大幅に遅れました。私が帰国した2021年3月の時点でも、新型コロナウイルス感染症の流行前のように、他のラボの研究者と直に会って自由にディスカッションしたり、コラボレーションができる日常は戻ってきてはいませんでした。それが、私の留学体験で一番残念だった点です。
 ラボのメンバーたちと2017年8月ごろに会食したシーン。新型コロナ禍のせいで、こうした機会は全く持てなくなってしまった。(妹尾氏提供)
ラボのメンバーたちと2017年8月ごろに会食したシーン。新型コロナ禍のせいで、こうした機会は全く持てなくなってしまった。(妹尾氏提供)
―――そのような状況からも、得られたものはありましたか。
妹尾 円滑なオンライン・コミュニケーションのために、電子ツールをうまく使いこなすノウハウでしょうか。例えば、ハーバード大学ではZOOMに加えて、「SLACK」というグループウエアを使用していました。1対1で個人メッセージが送れるほか、あるトピックについて複数人でテキスト会話をすることなどもできるツールです。ZOOMとSLACKをうまく組みあわせて活用することで、ロックダウン中であっても、ラボ内のコミュニケーションは良好に維持できていました。
実は、京都府立医科大学内分泌・免疫内科学部門の医局でも、このSLACKを使い始めています。米国滞在中に私から医局のメンバーにSLACKがとても使いやすいことを伝えて、帰国前に導入してもらったのです。日本でもまだまだ、対面のディスカッションやコラボレーションが制限される状況ですから、米国での経験を生かしてオンライン・コミュニケーションの充実を図りたいと思っています。
家族4人で渡米、小学生の子どもがバイリンガルに
――ボストンへは家族みんなで行かれたのですか。
妹尾 家族4人で一緒に渡米しました。妻は循環器医なのですが、私の留学に合わせてボストンで仕事を見つけることができました。子どもは渡米時、上は小学3年生、下は幼稚園生(年長)でした。
――お子様は米国の環境にうまく馴染めましたか。
妹尾 上の子は現地の公立小学校に編入しました。最初は英語が全く分からないし、やはり大変でした。しかし、しばらくすると友達ができて、現地の生活を楽しむようになりました。ボストンという土地柄も良かったと思います。米国内でもボストンは特に、多国籍な雰囲気が強いのです。公立学校には英語が主言語でない子ども向けのサポートプログラムがあり、助けられました。また、日本人の先生も1人いらっしゃり、ずいぶん支えてもらいました。
親としては、学校の先生と密に連絡を取ること、子どもの精神的なケアをしっかりすることに気を付けました。それから日本人ばかりのグループで固まってしまわないように、現地の子どもとの交流をサポートするよう心掛けました。
――具体的にはどのようにされたのですか。
妹尾 週末に学校の友達の家族と、家族ぐるみで公園にピクニックに行ったりしました。ボストンは自然が美しく、魅力的な公園がたくさんあります。緯度が北海道と同じくらいなので、夏でも野外で快適に過ごせます。冬は無料のスケートリンクに行って、スケートを楽しんだりもしました。
帰国時には、上の子は完全なバイリンガルになっていました。日本語で話すときは日本語で考え、英語で話すときは英語で考えているようです。今やその英語力は、全く親の比ではありません(笑)。ボストンの友達との交流は帰国後も続いていて、週末の早朝にはZOOMで長時間しゃべっています。新型コロナウイルス感染症が落ち着いたら、友人を訪ねたり、日本に招いたりするのを楽しみにしているようです。
渡米時に幼稚園生だった下の子は、英語を話すようになるのは早かったものの、忘れるのも早かったです。子どもに英語力を身に付けさせるという観点では、小学2~3年生くらいで渡米するのがベストではないかと思います。
 2019年9月に行った米国東海岸最北のメイン州にあるAcadia国立公園でのショット。サイクリング中の休憩スポットで走りぬけた山を見る。(妹尾氏提供)
2019年9月に行った米国東海岸最北のメイン州にあるAcadia国立公園でのショット。サイクリング中の休憩スポットで走りぬけた山を見る。(妹尾氏提供)
――最後に留学を検討している医師にアドバイスをお願いします。
妹尾 私は海外留学するのが遅かったのですが、実際に行ってみると、同じくらいの年齢で留学している医師もたくさんいました。キャリアを積んでからの留学は必ずしも不利ではなくて、臨床医として蓄えた経験や知識が、基礎研究においてもアドバンテージになります。「もう、今からでは遅い」などと諦めないで、肩に力を入れずに行ってみたら、得るものは相当大きいですよ。
英語でのコミュニケーションについても、「なんとかなるさ」くらいの気持ちでいいと思います。ラボでは、きれいな英語を話す必要は全くありません。最初の1年間はヒアリングにちょっと苦労しますが、必ず聞き取れるようになります。
家族で一緒に行くなら、子どもたちにとって海外での経験、英語力、現地でできた友人は一生の財産になると思います。私の家族はみんな、一緒に行って良かったと言ってくれています。
留学後の異例のラボ移籍を乗り越えて研究生活を続行
2021.12.15
米国留学で手にした基礎研究三昧の日々
小網 博之(こあみ・ひろゆき)氏
2004年金沢大学医学部卒。群星沖縄・浦添総合病院での初期臨床研修を経て、2006年 同病院救急総合診療部専修医。2007年日本医科大学千葉北総病院救命救急センター専修医。2009年浦添総合病院外科勤務。2012年佐賀大学医学部救急医学講座勤務。2018年から3年間、米テキサス州ヒューストンのMcGovern Medical School/UTHealthにポストドクトラルフェローとして留学。帰国後、2021年に佐賀大学医学部先進集中治療学講座 准教授として復帰。2022年より佐賀大学医学部先進集中治療学講座 教授(現職)。