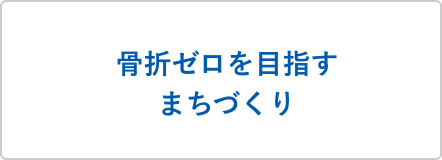専門にとらわれず広い視野から患者を診たいという思いから、救急医療の世界に進んだ小網博之氏。臨床で多忙な日を送りながらも、血液凝固に関わる基礎研究へ携わりたいという思いが強まっていたという。そして2018年、ほぼ独力で準備を進め、「39歳のポスドク」として米国テキサス州ヒューストンへの留学を実現した。
先生プロフィール
佐賀大学医学部 先進集中治療学講座
小網 博之(こあみ・ひろゆき)氏
2004年金沢大学医学部卒。群星沖縄・浦添総合病院での初期臨床研修を経て、2006年 同病院救急総合診療部専修医。2007年日本医科大学千葉北総病院救命救急センター専修医。2009年浦添総合病院外科勤務。2012年佐賀大学医学部救急医学講座勤務。2018年から3年間、米テキサス州ヒューストンのMcGovern Medical School/UTHealthにポストドクトラルフェローとして留学。帰国後、2021年に佐賀大学医学部先進集中治療学講座 准教授として復帰。2022年より佐賀大学医学部先進集中治療学講座 教授(現職)。
沖縄で実感したプレホスピタルケアの面白さ
──先生が救急医を目指されたのは、どのような理由からですか。
小網 私は石川県の豪雪地帯に生まれ育ちました。高校時代から抱いていた研究への憧憬が高じて、金沢大学医学部2年生から研究室に通い詰める学生時代を送りました。卒業した2004年は、奇しくも初期臨床研修制度が始まった年でした。
卒業時には、外科医になりたいとか内科医になりたいという希望は持っておらず、専門にとらわれず患者さんを診ることができる医師になりたいと思っていました。そうしますと選択肢は総合診療医か救急医ということになります。長く過ごした地元を脱出したいという思いもあり、研修先として目に留まったのが、沖縄県で始まったばかりの「群星(むりぶし)沖縄プロジェクト」でした。
群星沖縄プロジェクトは「良い医師を育てる」という目的のために、基幹型病院と協力型病院・施設で病院群を形成することで研修医教育を進めようという臨床研修病院群プロジェクトです。「自分のために始まったようなプロジェクトだ」と直感した私は、すかさず応募しました。救急に興味がありましたので、病院群の中でも救急医療に力を入れていた浦添総合病院で初期臨床研修を開始しました。
初期研修の2年間で、救急外来で患者を診る仕事が自分には合っていると感じ、後期研修でも引き続き救急部を選択しました。多くの救急症例を経験することができ、プレホスピタルケアの面白さを実感しました。特に浦添総合病院では、検査の前にバイタルサインから患者の状態を総合的に判断し、身体所見を通じてアセスメントを進めるといったことを徹底してたたき込まれました。このトレーニングが、今でも自分の血や肉となっています。
「より重症の患者が診たい」と千葉の大学病院へ
──沖縄で救急に携わった後、千葉県の日本医科大学千葉北総病院に移られたのは、どうしてですか。
小網 沖縄で救急総合診療医として勤務するうちに、「より重症の患者を診たい」という思いが募ってきたためです。沖縄県では交通事故が少なく、そのため重症の外傷患者が少ないのです。一方、日本医大千葉北総病院はドクターヘリを擁し、救急医療や災害医療に注力していることで有名であり、重症の外傷患者が集まる病院でした。そこで2007年からの2年間、同病院の救命救急センターで専修医として勤務することにしました。
千葉北総病院は大学病院であるため、学会で研究発表する機会にも恵まれ、救急医として充実した毎日を送ることができました。しかし次第に、ここでも物足りなさを感じるようになってきたのです。確かに重症外傷の割合が高く刺激的ではありましたが、自分が活躍できるのは患者搬入後のたった30分間。その後は、専門性を持った上級医による根本治療が行われ、私はそうした治療をサポートすることになります。ですから、私も早く根本治療ができるような専門性を持ちたいと思っていました。
そこで「救急外来で緊急開腹手術までこなせる外科的スキルの習得」を目指し2009年に浦添総合病院に復帰しました。30歳で外科医研修医となり、首尾良く1年で専門医を取得することができました。また、当時の上司が研究を重視していたため、学会発表や論文投稿する機会が増えました。救急や外科系の学会で症例報告が数件しかないテーマを掘り下げて研究すれば、一気に世界最先端の研究者になれる──。そんな研究の醍醐味を実感しました。
──そこから今度は佐賀大学に移籍されましたね。
小網 再び沖縄に渡り3年が経過した頃、千葉北総病院時代の上司であり、佐賀大学医学部救急医学講座教授に就任された阪本雄一郎教授よりお誘いを受けたのです。阪本教授の誘い文句は「千葉に帰る前に佐賀にリハビリに来なさい。研究も留学もできるから」という魅力的なものでした。
研究者人生に影響及ぼした「ROTEM」との出会い
──石川、沖縄、千葉、沖縄と移った後で、ようやく留学という言葉が出てきました。
小網 佐賀大学での目標は、学位取得と留学に定めました。5年間の研究で、学位を取得した「ラット熱傷モデルにおけるハプトグロビンの炎症ならびに凝固能への効果」をはじめ、「敗血症ブタモデルにおけるPMX-DHPの呼吸機能改善効果」や「3次元皮膚培養パッチの作成と新規熱傷治療法の開発」といった研究に携わり、それらの成果を学会発表や論文としてまとめ上げることができました。
この期間に、私の研究者人生に大きな影響を及ぼすことになる、外傷蘇生検査の「ROTEM(rotational thromboelastometry)との出会いもありました。2015年にタイで行われた外科手術のワークショップで、世界的に著名な外科医であるケネス・マトックス(Kenneth L. Mattox)教授が行った「外傷蘇生において最も信頼できる検査はROTEMだ」という講演を聞いたのがきっかけでした。
ROTEMは、全血を用いて血液の粘弾性を測定する検査です。ERへ搬送される多くの患者は、出血や梗塞が問題になることが多いのですが、ROTEMを駆使することによって標準凝固検査で分からなかった知見が得られるようになりました。例えば「急性期DIC(播種性血管内凝固症候群)診断基準の各因子の中で、外傷性DICを診断するのに最も信頼性の高い因子はどれか」という問題に答えを出すことができるようになったのです。
凝固異常研究で米テキサス州ヒューストンに留学
──留学にもこのROTEM研究が関係していますね。
小網 2016年に神戸で開催された日本集中治療医学会学術集会で、血液凝固線溶動態をグラフ化し評価する「TEG(thrombelastogram)」を用いた様々な研究を報告していたUT Healthのブライアン・コットン(Bryan A .Cotton)教授と面談する機会がありました。神戸のホテルで私自身の研究成果をプレゼンし意見交換を終えた後、コットン教授に「凝固異常研究が盛んなところはどこか」と尋ねたのです。
すると、米国のテキサス州ヒューストンとコロラド州デンバー、デンマークのコペンハーゲンの3カ所だという返事が返ってきました。私は米国に留学したいと考えていたので、ショック学会へ参加のため渡米した際、同時にヒューストンとデンバーを現地訪問しました。そして、実際に家族で生活することも総合的に判断し、ヒューストンに狙いを定めました。
私は雪国育ちですから寒さに慣れていましたが、妻は沖縄の出身なので、そこを考慮しました。また、同行する家族の生活のしやすさを考えれば、日本人が多いところがいいとも考えました。日本企業の進出が盛んで、4000人の日本人が在住しているヒューストンは、留学生も数多く集っており、その点でも都合が良かったのです。そして2018年に、39歳のポスドクとしての留学を果たしました。
基礎と臨床が強く連携した研究体制
──留学先はどのようなところでしたか。
小網 留学先に選んだCeTIR(Center for Translational Injury Research)は基礎研究部門と臨床研究部門を擁する施設でした。名門テキサス大学傘下のUT Healthに属する研究組織で、研究目標に「外傷患者に対する止血、蘇生、コンピュータを用いた意思決定などの次世代医療技術を研究、開発すること」を掲げていました。臨床研究部門の責任者は前出のコットン教授で、基礎研究部門はチャールズ・ウェイド(Charles E. Wade)教授が責任者でした。
私は、臨床から離れて基礎研究に没頭することを留学目的の一つに掲げていたので、ウェイド教授の下で研究に集中できたことは幸運でした。研究テーマは「重症外傷と先天免疫」と「血管内皮細胞に対するカテコラミンの保護作用」、「線溶亢進と血管内皮細胞傷害」としました。
 McGovern Medical School/UTHealthの面々と。(小網氏提供)
McGovern Medical School/UTHealthの面々と。(小網氏提供)
──研究生活はハードだったのではないですか。
小網 それが毎日、信じられないくらい規則正しい生活を送ることができました。毎朝6時に起床し7時に家を出て、朝のカンファレンスに参加。9時から研究を開始して17時には帰宅、23時に就寝する──といった具合でした。家族と夕食を取り、ゆっくり入浴し、子どもの宿題を見ることもできました。研究室からは、休日をしっかり取るように求められていたので、留学期間中の3年間で家族と一緒に4回の長距離旅行をすることもできました。
──順調な留学生活だったのですね。
小網 予期せぬ事態にも見舞われました。その最たるものが、現在も続くCOVID-19の流行です。2020年3月24日にヒューストン全域が人流を遮断するロックダウンに入り、外出も食料品などの買い出しや散歩以外は許されない事態になりました。当然、ラボも閉鎖されました。
ロックダウン中は、データ解析や文献整理しかできません。ミーティングもウェブ会議や電話会議に限られ、研究が思うように進みませんでした。滞在期限が6月末に迫っていたので、当時は「こんな中途半端な段階で帰国しても意味がない」と本当に焦りました。
しかしながら、5月になるとラボでの研究再開が許可され、申請していた10カ月間の滞在延長も認められ、研究に専念できるようになりました。滞在延長が認められ感謝したものの、少々残念だったのは、在宅ワークが基本となっていたウェイド教授とのコミュニケーションが減ってしまったことです。12月の成果報告も、ウェブを通してのものとなりましたが、こればかりは仕方ないものと考えています。
 ラボでの最終日にウェイド教授(左)らと記念撮影。(小網氏提供)
ラボでの最終日にウェイド教授(左)らと記念撮影。(小網氏提供)「行って還ってきたという達成感」が財産に
──COVID-19の流行という不測の事態に見舞われながらも、研究をまとめて2021年5月に帰国し、佐賀大学に復帰されました。振り返って留学生活をどのように感じていますか。
小網 米国では、日本でも望めなかった基礎研究中心の生活を送ることができました。留学によって海外の一流研究者とのコネクションもできましたし、現地の研究者との議論を通して新たな研究テーマを見つけられたことも大きな収穫でした。さらに、専門分野が異なる多くの日本人研究者らと家族ぐるみのつながりも生まれました。それから米国内を長期旅行するなど、家族との貴重な思い出を作れたことも大きいですね。
中でも留学によって得られた最も大きな財産は「行って還ってきたという達成感」です。恒常的に留学生を送り出す規模の大きな大学と異なり、佐賀大学では留学をするきっかけを作ること自体が容易ではありません。そのため学会などの交流機会を逃さず、留学経験者の体験を聞きながら、留学に向けた準備を進めていきました。
それでも実際に留学となれば、克服すべき課題は少なくありません。指導医の立場にいれば、臨床現場を離れることが難しいケースも多いです。そのため私は留学にあたり、学位取得前から上司や医局長と事前に何度も相談をしました。また、専門医などの取得や更新を控えている場合には、そのタイミングも考慮しなければなりません。学会活動の調整も必要で、渡米前に退会した学会もありました。
加えて、子どもの教育や、日本を離れている間、親の介護をどうするかなども考えなければなりませんでした。当然ですが、留学中は収入が減るために、経済的な面についてもしっかり算段をしておく必要があります。
 ハロウィーン間近に家族旅行で訪れた農場での一コマ。(小網氏提供)
ハロウィーン間近に家族旅行で訪れた農場での一コマ。(小網氏提供)
──最後に、若い先生方へのメッセージをお願いします。
小網 若い先生方に対して、私はいつも「3年先、10年先の目標を立てる」ことの大切さを説いています。救急医は臨床に忙しいのが常で、日常に追われる生活を続けていては留学することはできません。救急医としてのキャリア形成に留学が必要であると考えるのなら、長期的な視点に立って準備を進めることが必要です。
留学という目標を達成した私の次の新たなる目標は、この佐賀から1人でも多くの医師を海外留学に送り出すことです。
米ハーバード大で自由にディスカッションする雰囲気を体感
2022.01.17
ただいまドイツに留学中、欧州の大陸文化を実感
宮川 一平(みやがわ・いっぺい)氏
産業医科大学病院 第1内科学講座 助教
2005年産業医科大学医学部卒業、産業医科大学病院臨床研修医。健康保険直方中央病院(現福岡ゆたか中央病院)内科、産業医科大学病院膠原病リウマチ内科、北九州総合病院総合内科を経て、2013年産業医科大学第1内科学講座助教。2018年産業医科大学病院救急科助教、2020年4月より現職。2020年9月より産業医科大学を休職してフリードリヒ・アレクサンダー大学(FAU)エアランゲン=ニュルンベルク博士研究員。(写真は宮川氏提供)