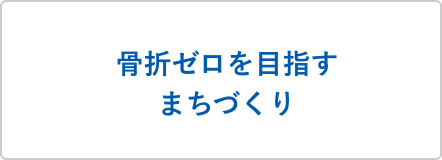神戸大学医学部整形外科の武岡由樹氏は、米国ハーバード大学関連病院のブリガム・アンド・ウィメンズ・ホスピタルに3年間留学した。学部時代から、医学・工学研究分野における「米国のすごさ」が何に根差しているのかを知りたかったと振り返る。留学してみて、日本とは大きく違うグラントやファンドの応募審査、世界中から研究者を引き寄せる研究施設のネームバリュー、社会に根付いた寄付文化などが米国の強みだとの思いを強くしたという。
先生プロフィール
神戸大学医学部整形外科
武岡 由樹(たけおか・よしき)氏
2009年神戸大学医学部医学科卒業、愛仁会高槻病院勤務(初期臨床研修)。2011年神戸大学医学部附属病院勤務。2012年国立病院機構神戸医療センター勤務。2013年製鉄記念広畑病院勤務。2014年兵庫県立こども病院勤務。2015年労働者健康福祉機構神戸労災病院勤務。2016年神戸大学大学院医学研究科(大学院)。2018年Brigham and Women’s Hospital/Harvard Medical School留学。2021年に現職復帰。
――武岡先生は昨年、米国留学から帰国されたのですね。
武岡 2018年9月に渡米して2021年9月に帰国しました。34歳から37歳まで丸3年間留学していました。留学先は米国ハーバード大学(Harvard University)の関連病院の1つであるブリガム・アンド・ウィメンズ・ホスピタル(Brigham and Women's Hospital)です。
――留学の経緯を教えていただけますか。
武岡 元々、神戸大学医学部整形外科学の先輩方は米国ピッツバーグ大学(University of Pittsburgh)にたくさん留学されていました。受け入れ先の教授にジェームス・ケイン先生(Dr. James D. Kang)という方がおられたのですが、そのケイン先生が2015年に、ピッツバーグ大学からブリガム・アンド・ウィメンズ・ホスピタルに移籍されたのです(Chairman of the Department of Orthopaedic Surgery, Brigham and Women's Hospital)。
私は、ブリガム・アンド・ウィメンズ・ホスピタルに当医局から派遣された留学生第1号ということになります。当時、医局の脊椎チーム・チーフであり、ケイン先生と特に親しかった西田康太郎先生(現・琉球大学医学部整形外科学講座主任教授)の推薦で留学が実現しました。西田先生は若い時分にピッツバーグ大学へ留学し、ケイン先生と一緒に研究していた経験をお持ちです。帰国後も家族ぐるみのお付き合いを続けていらっしゃったようです。私は当時、脊椎チームに所属する大学院生で、西田先生は直属の上司でした。
西田先生は、ご自身の留学体験がとても充実していたことから、後輩の医師にも積極的に海外に行ってほしいと常々思われていたようです。特に、ご自身がチーフを務めていた脊椎チームから定期的に米国に留学生を送りたいとのお考えがあったようで、ブリガム・アンド・ウィメンズ・ホスピタルのケイン先生の元に留学生を1人送れることになった際、脊椎チームに所属する私に「米国に留学したいですか」とお声掛けくださいました。それに対して私は「行きたいです」と即答しました。
――留学先での立場は、博士研究員(ポスドク)ですか。
武岡 実は渡米時、私はまだ大学院在学中であり、博士号が取れていなかったのです。しかし西田先生のお口添えとケイン先生のお計らいで、有給のポスドク待遇で迎えていただきました。長年の人脈などによって留学先で融通を利かせてもらえることは、医局からの留学の強みだと思います。
 ブリガム・アンド・ウィメンズ・ホスピタル整形外科チェアマンのジェームス・ケイン先生(左)と、研究を直接指導していただいたPI(主任研究者)の水野秀一先生(右)。(武岡氏提供)
ブリガム・アンド・ウィメンズ・ホスピタル整形外科チェアマンのジェームス・ケイン先生(左)と、研究を直接指導していただいたPI(主任研究者)の水野秀一先生(右)。(武岡氏提供)――西田先生からのお声掛けに即答したとのことですが、留学したい思いがずっとあったのですか。
武岡 学部時代から米国に留学してみたいと思っていました。「米国のすごさ」がどこからくるのか知りたかったのです。医学も工学もそうですが、米国では研究へのお金のかけ方、スピード感がすごい印象です。その仕組みがどうなっているのか、日本とは何が違うのかといったことはある程度長い期間米国で生活してみないと分からないでしょうから、留学してその疑問を解き明かしたいと考えていました。
体内と同じく高い静水圧下で椎間板組織を培養する研究を実施
――留学先ではケイン先生の指導で研究されたのですか。
武岡 ケイン先生は臨床医として毎週2~3日は手術をこなされ、さらに病院のマネジメントや人事にも関わるとても忙しい立場の方です。なので、ときどき研究報告をしてコメントをもらうくらいでした。私を直接指導していただいたのは、ケイン先生の下のPI(主任研究者)の1人の水野秀一先生(Associate Professor of Orthopaedic Surgery, Brigham and Women's Hospital)でした。
水野先生は30年ほど前に筑波大学大学院から米国に留学して来られ、そのまま定住された工学系のバックグラウンドを持つ研究者です。私は、水野先生が開発された細胞培養装置「ティッシュー・エンジニアリング・プロセッサー」を使って研究を行いました。
この装置は、細胞培養の際に、細胞にかかる物理的な圧力を制御できるのが特徴です。関節軟骨の培養に関しては、高い静水圧をかけて培養した方が品質の高い組織ができることを水野先生は明らかにし、再生医療向けの製品も開発されて治験を進めておられました。一方、椎間板も体内ではかなり高い圧力がかかって存在しているわけですが、細胞・組織培養についてはまだ分からないことが多かったのです。まずは生体内に似せた環境で椎間板の細胞を培養することが第一の課題で、その臨床的なメリットを調べることが次の課題という段階でした。
――武岡先生ご自身の研究内容について教えてください。
武岡 私の研究テーマは大きく2つありました。まず1つは、ウシの椎間板細胞を使って、ティッシュー・エンジニアリング・プロセッサーで静水圧をかける・かけない、さらにスキャフォールドとしてコンドロイチン硫酸プロテオグリカン(CSPG)などを加える・加えないといった培養条件の設定をして、どの条件が最も望ましいかを調べることでした。研究の結果、静水圧を高くしてCSPGを加える培養条件が、椎間板細胞培養に適していることが分かりました。この研究については既に論文発表しています。
もう1つは、手術検体として提供されたヒトの椎間板細胞について、ティッシュー・エンジニアリング・プロセッサーで静水圧をかけて培養した場合とかけないで培養した場合の組織の性質を比較する研究です。こちらについては現在、論文の投稿準備中です。
 水野秀一先生、ラボの仲間たちと記念撮影。(武岡氏提供)
水野秀一先生、ラボの仲間たちと記念撮影。(武岡氏提供)
研究資金が獲得できないラボは容赦なく取り壊し、PIは研究費確保に奔走
――米国で3年間の研究生活を送ってみて、「米国のすごさ」の疑問は解けましたか。
武岡 まず米国にはグラントや官民の投資ファンドが数多く存在し、日本とは投資規模の桁が違います。ただし、投資するかどうかの評価は日本以上に厳しく、ある程度実現可能性や成果が見えている研究でないと、なかなかお金が付かない印象です。お金が回らなくなるとラボは容赦なく取り壊しになるので、ラボのPIは研究費の獲得に一年中心血を注いでいます。すごい競争社会だと感じました。
ラボから給料をもらわずに働く無給の研究者がたくさんいることも、米国の研究力の源ではないかと思いました。その人たちは主に留学生で、出身国からグラントを得ているので本当の意味で無給ではないのですが、ラボは人件費を負担していません。研究施設のネームバリューで世界中から研究者を引き寄せ、そのマンパワーを使って一定のペースで研究成果を出す。成果を出すことで、継続してファンドやグラントのお金を獲得する──といった循環ができているように思いました。
それから、米国社会に根付いている寄付文化も、研究資金の潤沢さにつながっていると思います。患者さんが「〇〇の研究に使ってほしい」と非常に多額の寄付をすることが珍しくないのです。こうした寄付の背景として、文化・宗教的な面もありますが、一定以上の規模の病院には研究施設が備わっていて、腕のいい臨床医は基礎の研究室も運営していることが挙げられると思います。なお、寄付を受けた研究者が、寄付をしてくれた人に研究成果をしっかりと報告している点も印象的でした。
――研究結果以外にも、医局に持ち帰られた「成果」はありますか。
武岡 米国で研究を進める中で、あるレセプターに関連して新たな研究のアイデアを思いつきました。その1ネタを持ち帰れたのはよかったと思っています。現在、後輩の大学院生を指導して、研究を進めているところです。ほかにも、私自身が基礎的な領域の知識を整理できたことで、ある程度、自分で研究のストーリーを考えられるようになりました。そういった部分も今後、医局で生かしていきたいと思っています。
ボストンに日系スーパーマーケットが進出、食生活が劇的に改善
――ボストンの生活はどうでしたか。
武岡 やはり日本食が恋しくなるときがあります。本格的な「うま味」は米国の食材ではなかなか出せませんし、肉や野菜の好みも米国人と日本人では異なりますから。通販などである程度は日本の食材が手に入っていましたが、食事に関してはちょっと苦労していたのが本音です。しかし留学2年目に日本人経営のスーパーマーケットがコネチカットからボストンに進出してきて、食生活が劇的に変わりました。日本の納豆、練り物、お菓子なども容易に手に入るようになったのです。
スーパーで買った日本食材を使って、妻が様々な日本料理を作ってくれました。一番感動したのは「豚トロの塩ダレ」ですかね(笑)。米国人は基本的に赤身肉を好むので、普通の米国のスーパーでは脂が多い肉自体なかなか手に入らないのです。
米国の西海岸に比べると東海岸では日本食材が手に入りにくいと言われていました。これまで留学した日本人の中には、私のように食に戸惑った人もいたのではないでしょうか。しかし日系のスーパーができたことで、今後、ボストンの日本人の食生活はだいぶ安定すると思います。
――留学には、家族と一緒に行かれたのですか。
武岡 はい、妻と子ども2人の家族みなで行きました。当時5歳の長男と3歳前の長女は現地の保育園に通わせていたのですが、驚異的な速さで英語を話すようになってびっくりしました。電車やエレベーターで一緒になった見ず知らずの米国人の大人と会話したり、兄妹間で英語で話していたりと、私たち夫婦は驚かされてばかりでした。帰国後、下の子は少し英語を忘れてきていますが、上の子は維持しています。
 家族でハロウィーンにマサチューセッツ州北部のトップスフィールドに小旅行したときの様子。(武岡氏提供)
家族でハロウィーンにマサチューセッツ州北部のトップスフィールドに小旅行したときの様子。(武岡氏提供)
――お子さんが米国で身に付けた英語力を維持できるよう、帰国後、何かしてあげていますか。
武岡 小学校はアメリカンスクールなどではなく日本の学校に行かせていますが、放課後に英語で会話をする学童保育に通わせています。日本の文化的な背景はちゃんと身に着けてほしい一方で、英語にコンスタントに触れる機会も作ってあげたいと考えてそうしています。
英語力について、子どもたちは今スタートダッシュが切れた状態なので、少なくとも高校生くらいまではそれが維持できるよう今後もサポートをしていきたいです。将来、子どもたちが米国の大学行きたい、米国で働いてみたいといった希望を持ったとき、言語が障壁にならないようにしてあげたいと思っています。
――最後に、留学を考えている若い医師にアドバイスをお願いします。
武岡 留学期間中は時間に余裕が持て、自分のペースでいろいろなことを考えられました。振り返るとそれがすごくよかったなと思います。特に、米国でリサーチ・マインドや基礎研究の視点を養うことができました。帰国してからの臨床と基礎研究への取り組み方などについても、自分の頭の中が整理できました。家族と過ごす時間も日本にいるときよりかなり長く取れたので、家族との絆を深めるにもよい期間だったと思います。
留学するべきかどうかは、プラス面とマイナス面を自身がどう判断するか次第だと思います。お金もかかりますし、家族の生活など、個人個人の事情があるでしょうから、簡単な決断ではないと思います。しかし、代え難い経験が得られることも事実ですので、どうしようか迷っている人に対しては、「チャンスをつかんで行ってみたらどうですか」というのが私の意見です。
武岡氏の留学の成果となった論文
- In vitro nucleus pulposus tissue model with physicochemical stresses. Takeoka Y, Kang JD, Mizuno S. JOR Spine. 2020 Jul 1;3(3):e1105.
Augmented Chondroitin Sulfate Proteoglycan Has Therapeutic Potential for Intervertebral Disc Degeneration by Stimulating Anabolic Turnover in Bovine Nucleus Pulposus Cells under Changes in Hydrostatic Pressure. Takeoka Y, Paladugu P, Kang JD, Mizuno S. Int J Mol Sci. 2021 Jun 2;22(11):6015.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34199496/
米国留学で見て感じた有形・無形の文化を日本での仕事に生かす
2022.08.01
米国留学で低侵襲手術の世界的な流れを実感できた
手束 文威(てづか ふみたけ)氏
2007年自治医科大学卒業、徳島県立中央病院初期臨床研修医。2009年徳島県立三好病院。2011年那賀町立上那賀病院整形外科医長、那賀町国民健康保険木沢診療所所長。2013年徳島大学病院整形外科医員。2014年那賀町立上那賀病院整形外科医長、那賀町国民健康保険木沢診療所所長。2016年徳島大学病院整形外科特任助教。2018年徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学分野助教。2018年10月Northwestern University Feinberg School of Medicine Department of Orthopaedic Surgery, Visiting Scholar。2019年徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学分野助教。2020年徳島大学大学院医歯薬学研究部脊椎関節機能再建外科学分野特任講師。2021年徳島大学大学院医歯薬学研究部感覚運動系病態医学講座運動機能外科学(整形外科)講師。