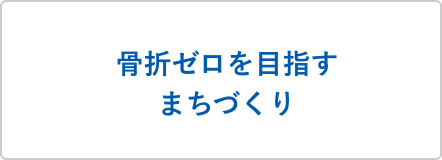北海道大学病院血液内科講師の後藤秀樹氏は、米国サンフォード-バーナム医学研究所に3年3カ月留学した。当初は無給の条件だったため蓄え資金が尽きたら帰国するつもりであったが、半年後に有給のポジションを得ることができたことが大きかったと振り返る。留学中には紆余曲折あったが、研究ばかりする日々でなく、時にラボの同僚とサーフィンや食事を楽しむなどプライベートも充実。米国で見たり感じたりした有形無形の文化を、帰国後の仕事に生かせているという。
先生プロフィール
北海道大学病院 血液内科
後藤 秀樹 氏
2002年近畿大学医学部卒業、北海道大学病院初期研修医。苫小牧市立総合病院消化器内科、市立札幌病院免疫血液内科、北海道大学病院第二内科を経て、2011年北海道大学大学院医学研究科病態制御学専攻博士課程修了、同大学病院血液内科医員。2012年Sanford-Burnham Medical Research Institute博士研究員。2015年北海道大学病院血液内科(臨床研究開発センター)特任助教。2017年同科助教、2020年同科診療講師。2022年北海道大学病院検査・輸血部講師。
――留学先と、留学の経緯についてご紹介をお願いします。
後藤 私は2012年1月から2015年3月までの3年3カ月間、米国カリフォルニア州サンディエゴ市のラホヤ(La Jolla)にあるサンフォード-バーナム医学研究所(Sanford-Burnham Medical Research Institute)に留学していました。ラホヤはサンディエゴ市街から車で15分ほど北に行ったところにある地区です。米国では海沿いの高級住宅地として有名ですが、研究施設が多く集まっていることでも知られています。
留学前は、北海道大学病院第二内科(血液グループ)に所属していました。2011年6月に大学院博士課程を修了後、チャンスがあれば海外留学してみたいと思い、留学先の情報収集を行っていました。すると、2カ月ほどしてサンフォード-バーナム医学研究所のジョン・リード(John Reed)研究室で血液がん領域に詳しい博士研究員を探しているとの情報を入手しました。
リード先生はBCL-2(B細胞リンパ腫2)の機能解析を行うなど、アポトーシス研究の分野では有名な研究者です。日頃から白血病や悪性リンパ腫といった「血液がん」に対する診療を行っていた私としては、アポトーシスという観点から血液がんの治療抵抗性機序について研究してみたいと考え、後先考えずにすぐに連絡してしまいました。
 サンディエゴ市のラホヤ地区に位置するサンフォード-バーナム医学研究所。(後藤氏提供)
サンディエゴ市のラホヤ地区に位置するサンフォード-バーナム医学研究所。(後藤氏提供)
――そしてウェブ面接に進まれたわけですね。
後藤 いえ、飛行機のチケットを取って、リード先生と直接話をするために米国へ飛びました。英語が苦手だったので、ウェブで面接を受けたらきっと不採用になるだろうと考えたのです。現地は1泊のみ、1泊3日の強行日程でした。
面接時間はよく覚えていませんが、たしか1時間くらいだったと思います。初めに、リード先生から研究内容などについて20分ほど説明されました。そして「ヒデキ、今日、私が説明したことは理解できたか?」と聞かれたのです。私は正直に「ほとんど分かりませんでした」と答えた上で、「ここで採用してもらえたら、誰よりも一生懸命頑張ります」と、意気込みを伝えました。
英語が不得意であったことに加えて、それほど顕著な業績も持ち合わせていなかった私からすると、おそらく採用されないだろうなと考えていたのですが、熱意が伝わったのか、無給を条件にリード研究室の一員として研究留学が認められました。無給だと留学されない方も多いかもしれませんが、楽観的な私は「留学してから考えよう」、「なんとかなるだろう」と考えて、リード研究室へ留学することに決めました。

渡米したばかりの頃にリード先生と。(後藤氏提供)
――すごい熱意ですね。その熱意の源は何だったのですか。
後藤 医局の先輩方の留学経験を聞いているうちに、自然と自分も行きたい気持ちが強くなっていたのだと思います。特に、当時、第二内科教授だった小池隆夫先生(現・北海道内科リウマチ科病院理事・最高顧問)の言葉は、とても心に残っています。「必ずしも研究成果が残せなくてもいい。海外留学して、有形無形の文化を見て感じてきなさい。旅行で1週間程度滞在するのと年単位でそこで生活するのとでは全く違う。40年以上にわたる長い医師の人生の中で、留学経験はきっと役に立つから」という小池先生からのメッセージは、留学に対する考えを大きく変えるものでした。
それまで私は、留学といえば研究業績を伸ばすために行くものと考えていましたが、「有形無形の文化を感じる」という言葉を聞いて、人としての感性を伸ばすこと、そして異文化での経験を積むことによる人生経験という意味で、他では学べない貴重な機会ではないかと考えるようになりました。このような背景もあって、留学への意気込みは強くなりました。
――留学で、臨床のキャリアに空白期間ができることについてはどう考えましたか。
後藤 30歳代のうちは多少遠回りしてでも色々なことを経験したいと考えていましたので、キャリアという点についてあまり意識はしていませんでした。私は当時34歳でした。年齢が高くなるにつれて留学は難しくなるので、このチャンスをつかみたいとの思いの方が強かったと思います。
働きぶりが認められて半年後から「有給」に
――留学資金については、無給でも問題なかったのですか。
後藤 実は当時、それほど貯金はありませんでした(笑)。そのため留学の期間は決めず、資金が続く限り米国に滞在して、資金が尽きたら帰国しようと考えていました。案の定、早々に資金が不足してきたのですが、半年経った頃に新たな研究プロジェクトへ参加することが決まり、多少なりとも給与が支給されることとなりました。渡米してから半年間、わずか2ドルのお菓子を買うことすら躊躇しながら生活していたため、このプロジェクトのお話を受けた時は本当にうれしかったです。
おそらく研究室の中でリード先生は、最初のうちは私の働きぶりを見極めていたのでしょう。使える研究者だろうと認識されたのかわかりませんが、いずれにしても、これで長期滞在の基盤ができました。仕事ぶりが認められて、その結果として給料をもらえるということが、こんなにうれしいことなのか……。日本では味わったことのない感覚でした。
――参加することになった研究プロジェクトについて教えてください。
後藤 同じくラホヤにあるスクリプス研究所のベンジャミン・クラヴァット研究室(Benjamin Cravatt, PhD;Gilula Chair of Chemical Biology, Professor, Department of Chemistry, The Scripps Research Institute)との共同プロジェクトでした。血液がん細胞がアポトーシスを起こす際に、どの細胞内タンパクが関与しているかを見つけることがプロジェクトの第1の目標です。つまり、血液がん細胞が生きていくために必要なもの、もしくは細胞死に重要なものを見つけ、最終的にはそれらの働きを阻害あるいは活性化する抗体や薬を開発することがプロジェクトのゴールでした。
研究の結果、血液がん細胞のアポトーシスに関連する4つのたんぱく質を同定し、そのうちの1つのタンパクに着目して機能解析を行うと同時に、特異的に結合する抗体の作製にも着手しました。
――留学先での研究成果は論文などにまとめられたのでしょうか。
後藤 いえ、実はまだ、この研究内容は論文発表できていないのです。プロジェクトは企業から研究資金の提供を受けながら行ったため、特許などの関係でデータの公開が制限されてしまったからです。留学で頑張ってきた成果を形にすることができないのは残念なので、時間はかかっても臨床検体を用いた研究に切り替えて、近い将来、論文化を目指したいと考えています。
もう1つ残念だったことがあります。それは、留学してちょうど1年が経った頃、リード先生が大手製薬会社にヘッド・ハントされたことです。それまでは研究内容についてリード先生と直接会ってディスカッションすることが可能でしたが、後半2年間はボスが不在の状況となり、ラボも徐々に縮小していくこととなりました。
留学先では様々なトラブルもありましたが、私自身は海外で留学生活を送ることができたことについて大変満足しています。とても勉強になることが多く、実りある留学生活だったと感じています。
 リード先生が大手製薬企業へ移る直前に撮影したラボメンバーの集合写真。(後藤氏提供)
リード先生が大手製薬企業へ移る直前に撮影したラボメンバーの集合写真。(後藤氏提供)自分の考えをきちんと伝える大事さを実感
――「有形無形の文化を見て感じてきなさい」という小池先生の言葉についてですが、達成できましたか。
後藤 米国の文化を、良くも悪くも色々知ることができたように思います。良いところは、米国人のオープンな気質、物事をポジティブに捉えて問題を建設的に解決しようとする点、頑張っている人をみんなで伸ばそうとするスタンスなどです。また、イエスかノーかをはっきり言うこと、たどたどしい言葉であっても何かを一生懸命伝えようとすれば、それを理解しようとしてくれる姿勢などもそうですね。
――留学して見てきたものや感じたものは、日本で仕事をする上で役立っていますか。
後藤 留学中にいろいろな人と接して話しをすることで、日本に居ては感じることができなかった様々な思想や考えがあることを学びました。多様性を感じることができたことは、人と接する職業である「医師」として重要な財産になったと感じています。また、メディカルスタッフの方々と一緒に働く際は「言わなくても分かってくれるだろう」で済まさず、自分自身の考えを必ず自分の言葉で伝えるようになりました。簡単なようで意外とできていないことだと思いますが、医療現場においては、インシデントを減らすためにもとても重要なことであると思います。
――ラボで親しくなった研究者の同僚はいましたか。
後藤 ラボで私の後ろの席に座っていた、インド人の女性研究者とはよく話をしました。彼女の方から、毎日ものすごく話しかけてくれたのです。「研究の調子はどお?」「これ美味しいから食べてみて」「隣の部屋の〇〇はいつもうるさい」など、話の内容は本当に他愛もないことでしたけれど(笑)。
彼女は小中高と英語で教育を受けたそうで、自分の考えを英語で話すことに全く不自由はないようでした。ただ、インドなまりの英語だったので、初めはとても聞き取りにくかったのですが、その英語を毎日聞き続けたことで、インド人の話す英語がスムーズに聞き取れるようになった一方、困ったことにネイティブの話す英語のリスニングはなかなか上達しませんでした(笑)。
それからオーストリア人の男性研究者とは、時々サーフィンに行きました。ラボから車で5〜10分ほどの距離に、とても素敵なビーチがあり、そこで彼からサーフィンを教わりました。全くの素人であった私は、なかなか上達せず、最後にようやくボードの上に立てたくらいでしたが、とても楽しかった思い出の1つです。

サンディエゴのビーチでラボの同僚と。(後藤氏提供)
先輩医師からの「そろそろ戻ってきたらどうだ」の呼びかけに帰国を決断
――ラボから給料がもらえるようになった後、留学期間についてはどう考えていましたか。
後藤 先にも述べましたが、お金が尽きたら帰国しようと考えていました。気がついたら結果として約3年経過していました。当科の先輩の中には4年間、5年間と研究留学される方もいるので、それほど長い方ではなく、本当にあっという間であったと感じています。
――すると帰国を決断したきっかけは何だったのですか。
後藤 2014年12月にサンフランシスコで開催された米国血液学会へ参加した際に、当時の医局長であった藤本勝也先生(現・北海道がんセンター血液内科・統括診療部長)から直接会って話をしようと持ちかけられました。そこで藤本先生から「そろそろ日本に戻ってこないか」というお誘いを受けました。まだ、研究が道半ばであった私にとって、できればもう少し長くアメリカで頑張りたい、という気持ちがあった一方で、貯金も徐々に底が見え始めており、家族にも迷惑をかけられないという思いもあり、とても複雑な心境であったことを覚えています。
海外で生活していると医局の先生と直接話しをする機会もほとんどないため、時々もう忘れられているかも……という感覚になることすらあります。そんな中、忘れられずに声をかけてもらえたことはとても嬉しく、これも良いきっかけかなと考えて帰国することにしました。
――最後に、留学を考えている若い医師にアドバイスをお願いします。
後藤 留学のメリット・デメリットはいろいろあると思います。それは人によって異なると思います。私が感じたメリットとしては、米国は研究施設が整っているので、日本とは違う研究所のシステムに触れてくるだけでも貴重な機会になることが挙げられます。また、人と話をするのが嫌いでなければ、英会話の勉強の機会もあちこちに転がっています。
私は、日本にいるときよりも家族と過ごす時間が長くなりました。家族が海外での生活に適応できれば、日々の生活はとても楽しくなると思います(あくまでも個人的な見解です)。一方で、家族が海外暮らしに慣れずに帰国してしまうケースもあるようですので、留学前も、留学してからも家族と話しをする時間を持つことはとても大事だと思います。
海外での暮らしには、不自由なことがいっぱいあります。治安が悪いこと、日本のような行き届いたサービスは期待できないこと、どこの事務も適当な人が多いこと、コンビニの質が異常に低いこととか(日本が異常にレベル高い!?)言い始めたらキリがありません。留学から帰国する直前、3年3ヶ月の米国で暮らしを振り返って思ったことは、「日本って本当にいい国だな」ということでした。留学先での不自由さはデメリットかもしれませんが、改めて日本の素敵なところを再認識できる良い機会でもありますので、日々の研究だけでなく、そういった面にも目を向けながら留学生活を満喫してもらえると良いと思います。
ただいまドイツに留学中、欧州の大陸文化を実感
2022.06.01
留学で医学・工学研究分野での「米国のすごさ」の根源が分かった
武岡 由樹(たけおか・よしき)氏
2009年神戸大学医学部医学科卒業、愛仁会高槻病院勤務(初期臨床研修)。2011年神戸大学医学部附属病院勤務。2012年国立病院機構神戸医療センター勤務。2013年製鉄記念広畑病院勤務。2014年兵庫県立こども病院勤務。2015年労働者健康福祉機構神戸労災病院勤務。2016年神戸大学大学院医学研究科(大学院)。2018年Brigham and Women’s Hospital/Harvard Medical School留学。2021年に現職復帰。