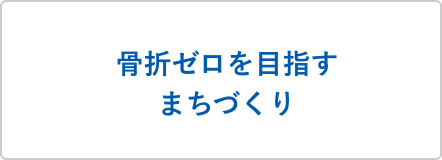札幌医科大学血液内科学助教の池田博氏は、ハーバード大学付属ダナファーバーがん研究所に2006年4月から2009年9月までの3年半、留学していた。13年を経て、海外留学は、自身の専門領域を多発性骨髄腫とすることに決めた契機だったと振り返る。また、研究者が活発に意見交換したりコラボレーションしたりする米国の文化に触れたことは、帰国後の研究方針に良い影響を与え続けているとのことだ。当時のラボの同僚との交友も続いているという。
先生プロフィール
札幌医科大学 血液内科学
池田 博(いけだ・ひろし)氏
2000年札幌医科大学医学部卒、第一内科研修医。2001年市立赤平総合病院内科医長。2002年札幌医科大学医学研究科大学院。2005年札幌医科大学第一内科学講座診療医。
――留学期間と留学先から教えてください。
池田 留学期間は2006年4月から2009年9月までの約3年半です。留学先は、米国ハーバード大学付属のがん専門研究機関である、ダナファーバーがん研究所(DFCI:Dana-Farber Cancer Institute)の中にあるジェローム・リッパー・マルチプル・ミエローマ・センター・アンド・レボウ・インスティチュート・フォー・ミエローマ・セラピューティクス(The Jerome Lipper Multiple Myeloma Center and LeBow Institute for Myeloma Therapeutics)です。DFCIは基礎研究と臨床試験の両方の機能を担う研究機関で、ハーバード大学のがん関連研究において非常に重要な施設に位置付けられます。ボストンのメディカル・エリアの一角にあり、周囲にはハーバード大学関連の他の医療機関もたくさん集まっていました。
ラボの研究責任者(PI)はケネス・C・アンダーソン先生(Kenneth C. Anderson, MD, Kraft Family Professor of Medicine, Harvard Medical School)でした。アンダーソン先生は、当時から多発性骨髄腫研究の第一人者であり、数々の臨床試験のコーディネートをされていました。米国血液学会(American Society of Hematology)の学会長を務めていたこともある方です。世界的に有名なラボだったので、イタリアやフランス、トルコなど欧州からも多くの留学生が来ていました。
――どのような経緯で、DFCIに留学することになったのですか。
池田 私は札幌医科大学医学部を卒業後、第一内科に入局しました。第一内科には臨床・研究チームとして大きく3つ、「消化器」「血液」「リウマチ」があります。私は当時から血液チームに配属されてはいたものの、大学院では消化器疾患関連の研究もするなど、まだ完全に所属チームが確定したわけではありませんでした。大学院での研究を進める中で興味が出てきた血液疾患の研究を、もう少ししっかりやってみたいと思い、留学を考えたのです。
 医局の先輩医師である安井寛氏(左)に招かれDFCIを見学(写真は池田氏提供)
医局の先輩医師である安井寛氏(左)に招かれDFCIを見学(写真は池田氏提供)ちょうどその時期(2005年頃)、医局の先輩医師である安井寛先生(現・聖マリアンナ医科大学血液・腫瘍内科特任准教授)がDFCIに留学中でした。連絡してみたところ、安井先生はそろそろ帰国を考えているとのことで「見学に来てみたらどうですか」と言ってくださったので、休みを取って行ってみることにしました。
実際にDFCIを見て、とても良い研究環境だと感じました。それで1年間ほど準備期間をおいて、安井先生と入れ替わる形で私がDFCIに留学したという経緯です。
留学までの1年間で、留学先で必要な実験手技を習得
――留学するまでの1年間、どんな準備をしたのですか。
池田 留学先で困らないよう、実験手技をもう少し学んでおこうと考えました。DFCIを見学して思ったのは、日本の大学院と比べて、研究の進め方に大きなギャップがあるということでした。日本の大学院では、午前中は病院で臨床をやって、午後から研究をしていました。基本的に臨床が優先なので、病院が忙しくなると予定していた実験ができないこともありました。しかしDFCIでは、プライベートな時間を除いて全ての時間を研究に費やすことができます。安井先生からも「研究の進むスピード感が日本にいるときとは全然違う」「学位を取って留学するなら、一通りの実験手技はマスターしているものと見なされる」と言われました。
私は、学位論文の研究で使わなかった実験手技は、十分に習得していませんでした。そこで留学までの約1年間で、免疫染色やウエスタンブロットなど、留学先で必要になりそうな実験手技を改めて勉強して実施できるようにしておきました。これは非常に役立ちましたので、やっておいてよかったと思いました。
――留学資金はどうされましたか。
池田 有給のポジションを得ることができました。ボストンは特に物価が高いので、給料で生活費の全てを賄うことはできませんでしたが、それでもだいぶ助かりました。アンダーソン先生からは「給料が出ない可能性もあります」と言われていたのですが、渡航の1カ月ほど前に出ることが決まりました。現地では無給で留学している日本人にも会いましたが、やはり大変そうでした。
――無給でも留学しようと考えていたのですか。
池田 給料が出なくても行くつもりでした。そのためにある程度、貯金もしていました。ただ、無給だったら3年半の滞在は難しかったと思います。2年くらいで貯金が底をついて、帰って来たのではないでしょうか。
――研究内容について教えてください。
池田 私が所属していたラボでは、製薬会社が創薬した新薬候補が多発性骨髄腫にどのようなメカニズムで効くのか、どの程度効くのかを検証していました。私の1つ目の研究は、抗体に毒素を付けた新薬候補の効果を検討したものです。3種類の新薬候補について動物実験まで実施して、論文にまとめました。
もう1つは、PI3-キナーゼ(Phosphoinositide 3-kinase)をブロックする新薬候補についての研究です。PI3-キナーゼは、がんの標的として知られるAKTパスウェイの上流にある酵素で、これをブロックすればAKTパスウェイをブロックできることを明らかにしました。さらに、この新薬候補がAKTパスウェイだけでなく、他のパスウェイも抑制することを明らかにして論文にまとめました。大きくはこの2つが、留学先での私の業績になります。
アンダーソン先生の「門下生」になり専門を多発性骨髄腫にしようと決意
――留学から13年ほど経った現在、振り返ってみて、留学はどのように役立っていますか。
池田 まず自分自身の専門を決める上で、留学には大きな意味がありました。先ほども言ったように留学前から血液チームに配属されてはいたものの、まだ確定はしていませんでした。留学を経て自分の専門を血液疾患に、さらにその中でも多発性骨髄腫にしようと決めました。
やはり多発性骨髄腫の世界的な権威であるアンダーソン先生の「門下生」と見られるので、それに恥じない臨床医、研究者にならなければいけないと思い、決意しました。札幌医大に復帰後は、多発性骨髄腫の患者さんが来られたら、私が中心になって診るようになりました。
もう1つは、コラボレーションに対する垣根が低くなったと思います。DFCIでは他のラボを気軽に見学に行ったり、コラボレーションの相談をしに行ったりすることができました。研究者が1人で考えつくことには限界があります。研究者が2人いたら考えていること、やりたいこと、得意な手技などが違うので、世界が広がります。留学前はそういった発想が全くできませんでした。特に大学院で研究しているときは、指導教員との間でやり取りをするだけでした。帰国してからは、自分で分からないことは病理の医師や基礎研究の研究者に積極的に聞きに行って、自分からコラボレーションを持ちかけることも自然とできるようになりました。
それから臨床に関してですが、アンダーソン先生の診察の様子を見せてもらい、自分の診察に取り入れたところがあります。アンダーソン先生はすごく優しい方で、患者さんの話を、とにかくよく聴くのです。「患者さんの気持ちに寄り添い、とても丁寧に診察する医師だな」と感じたのを鮮明に覚えています。多発性骨髄腫は骨折が起こることも多く、日常生活が難しくなる方が結構いらっしゃいます。私もアンダーソン先生の診察を思い浮かべながら、患者さんや家族の話をできるだけしっかり聴いて、どの程度日常生活がしにくいのか、ごはんはどれくらい食べられているのかといった情報を引き出し、診療に生かすよう心がけています。
 ラボの仲間たちとの記念撮影。上の写真の前列中央がPIのケネス・アンダーソン氏。(池田氏提供)
ラボの仲間たちとの記念撮影。上の写真の前列中央がPIのケネス・アンダーソン氏。(池田氏提供)――当時の同僚との関係、人脈は続いていますか。
池田 留学から13年経ちますが、同じラボで働いていた仲間とも、他のラボに留学していた日本人研究者らとも交流は続いています。同じ時期に留学していた研究者は、互いに「かけがえのない仲間」といった気持ちを持つものです。帰国後も電子メールのやり取りをしていましたし、新型コロナウイルス感染症のアウトブレーク前は、国際学会などで会う機会もありました。
――国際学会で会ったらどんな話をするのですか。
池田 「最近、研究の調子はどうだい」といった話題から、それぞれの国でどんなアニメが流行っているかといった雑談までいろいろです。新型コロナが落ち着いたら、また集まりたいですね。
NBAのボストン・セルティックスの試合観戦も堪能
――ボストンで、お気に入りの場所はありましたか。
池田 私は留学前からバスケットボールが大好きだったのですが、ボストンにはボストン・セルティックスという、当時も今もものすごく強いNBA(National Basketball Association)のプロ・チームがあります。本拠地は、ボストンのダウンタウン近くにあるTDバンクノース・ガーデンというアリーナです。3週間に1回くらい試合をやっていたので、観戦に行っていました。もちろん今でも、ボストン・セルティックスのファンです。日本人の八村塁選手が所属するワシントン・ウィザーズの試合もテレビで見ますが、一番応援しているのはボストン・セルティックスです。2022年6月までの昨季は、NBAの決勝まで行ったのですが、ゴールデンステート・ウォリアーズに敗れて優勝を逃してしまい、残念でした。
MLB(Major League Baseball)のボストン・レッドソックスの本拠地球場であるフェイウェイ・パークも、自宅から徒歩5分ほどの近くにありました。当時は松坂大輔選手、岡島秀樹選手がレッドソックスに所属していました。私の両親がボストンに遊びに来た時、ちょうど松坂選手が先発するというので一緒に見に行ったのは良い思い出です。
――ボストンは住みやすかったですか。
池田 住みやすかったですね。気候は札幌と同じような感じです。「東京と比べるとものすごく寒い」と他の日本人留学生は言っていましたが、北海道と比べると全然、大したことはありません。
――最後に、留学を考えている若い医師にアドバイスをお願いします。
池田 「留学したいんだけど」と家族に話すと、最初は反対されることが多いようです。私の妻も最初は反対していましたが、留学がスタートして現地の生活環境に慣れてからは、米国滞在をしっかり楽しんでくれました。帰国する時には「もう帰らないといけないのか……」「もっと居たいね」と言っていたくらいです。当初は家族が留学にあまり乗り気でなくても、粘り強く話し合ってみてください。
留学することが決まったら、自分独自の研究テーマをいくつか考えて留学先に持って行くとよいと思います。留学先での研究テーマはラボのPIから提案されて決まることが多いですが、留学生が提案した研究テーマとPIがやりたいことが合致すれば、それが採用されたり、提案された研究テーマと並行して実施できることもあります。そうなったらモチベーションも高まるし、いろいろな人から自分の研究にアドバイスがもらえるので、とても有益です。私も1つだけですが、自分自身の研究テーマを持って行き実施しました。独自の研究テーマをあと幾つか用意して留学すればよかったなと、今は思います。
英語力の有る無しは、大きな問題にはなりません。ラボの研究者は英語が母国語の人ばかりではないので、英語が完璧でないのはお互い様です。最初は聞き取れなくても、何度も聞き返したり、情熱を持って話しかけたりすれば、何とかコミュニケーションは取れます。最初の半年くらいは思うように英語が聞けず話せないと思いますが、ラボ内で発表をしたり、自分から質問したりする機会が増えるにつれて、自然と会話はできるようになっていきます。
コロナ禍で海外留学に行く人が少なくなってきているようです。以前よりも決断が難しくなっているのは確かだとは思いますが、研究に没頭できる環境が作りたい人にとっては、海外留学は非常にためになると思いますよ。
ピンポイントでリウマチと神経内分泌免疫学の研究ができるラボへ留学
2023.01.05
父の留学でドイツ滞在を経験、今度は自身が研究者として米国に
三木 春香(みき・はるか)氏
2008年筑波大学医学専門学群医学類卒業、筑波大学附属病院初期研修医。2010年筑波大学附属病院膠原病リウマチアレルギー内科入局。2011年筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科入学。2014年日本学術振興会 特別研究員 DC2。2016年筑波大学医学医療系助教。2017年日本学術振興会 特別研究員RRA、La Jolla Institute for Allergy and Immunologyへ留学。2022年より現職に復帰。