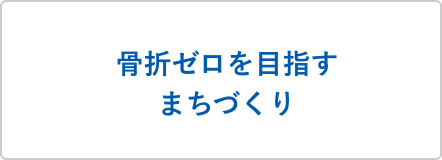山形大学大学院医学系研究科内科学第三講座血液・細胞治療内科学分野講師(山形大学医学部附属病院血液内科医長、同第三内科病院教授)の東梅友美氏は、米国に10年5カ月にわたり留学していた。移植片対宿主病(GVHD)のメカニズム解明に取り組み、多くの成果を上げて2017年に帰国。英語力向上とコミュニケーションも自身のチャレンジと位置づけ、ラボ内だけでなく、学会会場や日常生活でも様々な人と積極的にコミュニケーションを取ってきた。米国で培った人脈は、帰国後も自身の強みになっていると話す。
先生プロフィール
山形大学大学院医学系研究科
内科学第三講座
血液・細胞治療内科学分野
東梅 友美(とうばい・ともみ)氏
1999年山形大学医学部医学科卒業、石巻赤十字病院研修医。2001年社会医療法人北楡会札幌北楡病院血液内科医員。2002年北海道大学病院血液内科、北海道大学大学院医学研究科癌医学専攻。2006年米国ミシガン大学内科学講座血液腫瘍内科学分野リサーチインベスティゲーター。2014年3〜8月、米国サウスカロライナ医科大学研究助教授。2014年8月米国ミシガン大学リサーチインベスティゲーター。2017年山形大学大学院医学系研究科内科学第三講座血液・細胞治療内科学分野助教。2017年山形大学大学院医学系研究科内科学第三講座血液・細胞治療内科学分野学部講師。2019年山形大学大学院医学系研究科内科学第三講座血液・細胞治療内科学分野講師、山形大学医学部附属病院輸血・細胞治療部副部長。2019年山形大学医学部附属病院血液内科医長、同第三内科病院教授。
――留学期間と留学先から教えてください。
東梅 私が留学したのは2006年11月から2017年3月までの10年5カ月です。半年ほど別のラボで研究していた期間がありますが、それ以外はずっと、米国ミシガン州アナーバ市にあるミシガン大学で、PIを務めていたパヴァン・レディ先生(Dr. Pavan Reddy:現Director, Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center, Baylor College of Medicine)のラボに所属して基礎研究をしていました。
――長期間の留学だったのですね。
東梅 10年以上の長期になるとは思っていませんでした。留学前、私は北海道大学血液内科の医局に所属していましたが、3年か、長くても5年ほどで帰って来るつもりでした。
――留学の経緯を教えてください。
東梅 私の学位研究のテーマは、同種造血幹細胞移植の移植片対宿主病(GVHD)のメカニズムについてでした。ノックアウトマウスを使って、GVHDのメカニズムの解析と新規治療法開発に取り組んでいました。大学院でやってきた研究を応用、発展させられる留学先ということで、レディ先生のラボに留学することになりました。
――GVHDを研究テーマに選んだ理由は何だったのですか。
東梅 私が最初に造血幹細胞移植の患者さんを経験したのは札幌北楡病院でした。当時、副院長を務めていた笠井正晴先生(現・北海道鍼灸専門学校理事長)に移植医療を学びました。移植後、短期間に皮膚が真っ赤になる患者さんがいて、それがGVHDだったのです。今でこそ、いろいろな治療法が登場してきていますが、当時はまだGVHDのメカニズムもよく分かっておらず、治療法はステロイド投与だけでした。ステロイドが効かなくなったら患者さんはもう助からないといった時代で、私はGVHDの患者さんを診るのがすごく怖かったのです。なんとかGVHDを制御して、患者さんを救いたいと思ったのが、研究に取り組み始めたきっかけです。
大学院ではノックアウトマウスの移植モデルを使い、MIF(マクロファージ遊走阻止因子)がGVHDに関連していることをある程度突き止めたのですが、1つの分子だけをターゲットにしているとGVHDの全体像がつかめないな、との思いがありました。
――留学したい気持ちは医学部時代から持っていたのですか。
東梅 医学部生の頃は英語が全く話せず、自分が留学するイメージはありませんでした。しかし札幌北楡病院で笠井先生から「絶対留学した方がいい」と再三言われているうちに、留学を意識するようになったのです。笠井先生はUCLA(University of California, Los Angeles)に留学した自身の経験から、留学は視野が広がるし大きなチャレンジになるとおっしゃっていました。
留学を意識するようになったもう1つの要因は、結婚したことです。妻の姉が米国に住んでいたため、妻は米国に行きたかったようで「早く留学しましょうよ」と言われていました。
――ミシガン大学を留学先に選んだのは、どういった経緯だったのですか。
東梅 現・北海道大学血液内科教授で、当時は九州大学医学部第一内科所属だった豊嶋祟徳先生に紹介してもらったのです。豊嶋先生と私は研究分野が同じで、当時の厚生労働省の同じ研究班に所属していた縁もあり、ちょくちょくお会いしていました。会うたびに「どこかいい留学先はありませんか」と話をしていたところ、あるとき電話がかかって来て、「ミシガン大学のレディ先生が独立してラボを持つことになった。ついては研究者を探しているのだけれど、東梅君、行ってみないか」と、声を掛けてくださったのです。豊嶋先生は、ミシガン大学のジェームス・L・M・フェラーラ先生(Dr. James L. M. Ferrara:現Icahn School of Medicine at Mount Sinai)のラボに留学していました。レディ先生とは同じラボで一緒に働いていた同僚だったとのことです。
Reddy Labの初期メンバー(2007年)。後列中央がレディ氏。(東梅氏提供)
ミシガン大学BMTプログラム(2008年)でラボのメンバーと記念撮影。前列左から東梅氏、レディ氏、フェラーラ氏。(東梅氏提供)
仮説を外れたデータの原因を追究し大きな発見に
――東梅先生は10年5カ月の留学期間中に多くの成果を上げられ、多数の論文を発表されていますね。代表的な業績をいくつか紹介していただけますか。
東梅 まず1つ目は、留学して最初の頃に手掛けた研究です。移植の際に、ホストの樹状細胞以外、例えば腸の上皮細胞なども抗原提示細胞として働き、GVHDを発症することを示した内容で、当時としては非常に画期的だったと思います。
実はこの研究は、別の目的で始めたものでした。オス特有の抗原(H-Y Ag)を発現している腫瘍細胞に特異的なT細胞をマウスに投与した際の樹状細胞を介した腫瘍効果(クロスプレゼンテーション)を検討するはずだったのですが、このT細胞を移植するとGVHDの症状が出て1週間から10日ほどで全て死んでしまったのです。これでは実験は成り立たず想定外の結果でした。実験結果を報告するとレディ先生は、「そんなことが起るはずはない」と驚いていました。
この原因として、当初は宿主の血液細胞由来の抗原提示細胞が抗原提示をすることによりGVHDが起きたと思われました。しかし、ホストの樹状細胞のみをメス由来(キメラマウスと言いますが)にしても、同じようにGVHDが起きたので、「何かおかしい」とその理由を解明しようと研究を進めたのです。
研究の結果、ホストの血液由来の樹状細胞が機能していなくても、腸管の上皮細胞、内皮細胞などが抗原提示をすることが分かりました。GVHD発症のメカニズムについては、炎症が起こると腸の上皮細胞などでクラスⅡの発現が高まり、誘発されることを解明しました(下に参考文献)。
参考文献:Toubai, T., Tawara, I., Sun, Y., Liu, C., Nieves, E., Evers, R., Friedman, T.M., Korngold, R., Reddy P. Induction of acute graft-versus-host disease by sex-mismatched H-Y antigens in the absence of functional radio-sensitive host hematopoietic-derived antigen presenting cells. Blood 2012; 119: 3844-53.
2つ目は、GVHDの炎症の制御に関する研究です。私は当時から、GVHDは移植前処置の段階から始まっていると考えていました。前処置による組織傷害でサイトカインストームおよびホスト由来の抗原提示細胞の活性化が生じ、そのような炎症状態の中にドナー由来T細胞を輸注することでT細胞が活性化されるのではないかという仮説を立てていました。火に油を注ぐ感じですね。この仮説の下、GVHDを制御する方法を明らかにしようと実施した研究です。
当時、「Siglec-G(シアル酸結合免疫グロブリンG)」という分子が自然免疫応答を制御することは分かっていたのですが、ドナーT細胞を介した同種免疫を調整するかどうかについては分かっていませんでした。私は、モデルマウスを使った実験により、ホストの抗原提示細胞に発現しているSiglec-Gとドナー由来T細胞上のCD24が連携(SIglec-G-CD24 経路)してこの経路が活性化されると、GVHDによる炎症が軽減されることを明らかにしました(下に参考文献)。
参考文献:Toubai, T., Hou, G., Mathewson, N., Liu, C., Wang, Y., Oravecz-Wilson, K., Sun, Y., Choi, S.W., Fang, D., Zheng, P., Liu, Y., Reddy, P. Siglec-G-CD24 axis controls the severity experimental graft-versus-host disease. Blood 2014; 123: 3512-23.
――この研究結果は、どのように臨床応用され得ると考えられますか。
東梅 GVHDを軽減する薬剤の開発につながる可能性があります。将来的には、Siglec-Gを前処置開始から移植1週目くらいまで投与することで炎症が抑えられ、GVHDを軽減することができるようになるかもしれません。特に、骨髄破壊的な強い前処置が必要な患者さんには、軽減効果が高いのではないかと期待しています。
3つ目の研究は、腸GVHD発症のメカニズムについてです。私の研究テーマのほとんどは樹状細胞絡みだったのですが、1つ目の研究を通じて臓器特異的なGVHDの発症メカニズムも大切だとわかったため、手掛けることにした研究です。「NLRP6」と呼ばれるたんぱく質について、GVHDとの関連を調べました。NLRP6については、腸内細菌叢との相互作用により、自然免疫応答や胃腸の恒常性維持に役立っていることが、当時、既に知られていました。
ですからGVHDに関しても、炎症の緩和に作用しているのではないかと仮説を立てて実験を始めたのです。ところが実際には、NLRP6は腸GVHDを悪化させることが分かりました。その作用は、腸内細菌叢に依存していないことも明らかになりました(下に参考文献)。
参考文献:Toubai, T., Fujiwara, H., Rossi, C., Riwes, M., Tamaki, H., Zajac, C., Liu, C., Mathew, AV., Byun, J., Oravecz-Wilson, K., Matsuda, I., Sun, Y., Peltier, D., Wu, J., Chen, J., Seregin, S., Henig, I., Kim, S., Brabbs, S., Pennathur, S., Chen, G., Reddy, P. Host NLRP6 exacerbates graft-versus-host disease independent of gut microbial composition. Nat Microbiol 2019; 4: 800-12.
――1つ目と3つ目の研究は、仮説と違うデータが出たところからその現象を突き詰めて、大きな発見につなげたのですね。
東梅 そうですね。それは非常に大事な点です。実験を始める際に、仮説は必ず立てます。しかし想定外の結果が出た時には、その実験データを信じて、真摯に向き合うことが大事だと私は思います。その前提となるのは、自分自身の実験手技の確かさです。自分自身が自分のデータを信じられるように、またボスに「私のデータを信じてください」と言えるように、研究者は実験手技を磨かないといけません。そのことは現在も、若い先生方によく言っています。


「やるべきことを突き詰めてやり切ろう」と留学延長を決断
――長くても5年ほどと考えていた留学期間が、長期になったのはどうしてですか。
東梅 最初の2〜3年は、3つのテーマの研究を並行して手掛けていたのですが、あまりうまくいきませんでした。良いデータが次々に出始めたのが3〜4年目でした。それで研究にはまったというか、帰国するのがもったいなくなりました。1年目の滞在費は日本で獲得した奨学金で賄ったのですが、2年目以降はラボから給料が出るようになったし、米国の学会のグラントも獲得できたりしたので、お金の心配はありませんでした。
それから、留学5年目の2011年に起きた東日本大震災も決断に影響しました。個人的な話なのですが、岩手県の私の地元の町も被災して、実家が無くなり、母は今も行方不明です。役場で働いていた高校の同級生も亡くなりました。私も地元の病院で働いていたら死んでいたのではないかと考えました。人生がいつまで続くかは誰にも分かりません。悔いが残らないように、今、自分がやるべきことを突き詰めてやり切ろうと思ったのです。
――10年たって帰国を決断した理由は何だったのでしょうか。
東梅 ある程度、米国でやるべきことはやり切ったと自分で納得できたということです。米国にとどまり、ずっと研究の仕事をしようかと考えた時期もありましたが、やはり日本で臨床医をやりたい思いが強かったのです。帰国するなら10年が一区切りかなと。それ以上たってしまうと、臨床医に戻るのがより大変になるだろうと考えました。あとは子どもの教育についてです。米国で生まれて米国の文化の中で育ってきたので、日本の文化に少しでも触れさせたいとの思いがありました。
――帰国することになって、レディ先生には何と言われましたか。
東梅 「米国に残ってくれ」と最後まで言われていました。「君の研究者としての将来は私が保証するから」「家族のサポートもするから」と。本当にありがたかったです。レディ先生とは歳も近く、もともと親しみやすい人でした。ただ研究に関しては、一般的なアメリカのボスと同様に仮説を重視する傾向が強く、私が仮説と違うデータを出すとなかなか理解してもらえない時期もありました。しかし滞在の最後の数年間は、「仮説に合わなくても、君が出したデータなら信用するよ」と言ってくれていました。完全に信頼関係ができていましたね。
帰国後も交流は続いています。共同研究もしていますし、論文を書いた時にはサジェスチョンをお願いすることもあります。将来的には、医局の後輩医師をレディ先生のラボに留学で送り出したいですね。

英語とコミュニケーションにもチャレンジ、育んだ人脈が現在の強みに
――留学期間中、研究以外でもチャレンジしたことはありましたか。
東梅 一番のチャレンジは「英語」と「コミュニケーション」だったと思います。どれだけ自分の英語が理解してもらえるようになるか、そのために努力してきました。また、英語が下手なりにコミュニケーションがしっかり取れるように、日常でも学会でも、積極的にいろいろな人に話しかけることを心掛けてきました。その結果、米国人のみならず世界各国から来ている人と友達になれたことが私の自慢で、強みにもなっています。現在も、学会で話しかけた縁で仲良くなったベルギー人研究者と、共同研究をして論文を書いているところです。
日本の若い研究者から、「共同研究の相手が見つからない」と悩み相談のメールが来るので、ちょくちょく橋渡しみたいなこともしています。このインタビュー記事を見た方の中にも、同じような悩みを抱えている人がいれば、ご連絡いただければ相談に乗りますよ(笑)。
――米国での暮らしはどうでしたか。
東梅 アナーバーはデトロイトから60kmほど、カナダのトロントから450kmほどの距離で、5大湖の1つエリー湖の近くにあります。毎日だいたい夕方7時頃には帰宅していました。ニューヨークよりも緯度が高く、冬は日が短いのですが夏は夜9時過ぎまで明るいので、帰宅後、子どもと一緒に近くを流れているヒューロン・リバーにブラックバスを釣りに行ったり、自宅の庭先でバーベキューをしたりと楽しみました。休日には近くの公園にピクニックに行ったほか、アップルピッキング、ストロベリーピッキングなどにも行きました。アナーバーは田舎町ですが、その土地なりの生活を楽しむことができました。
――お子様の教育について、気を付けていたことはありますか。
東梅 地球上にはいろんな人種がいて、みなが協調しながら社会が回っているんだ、だからお互いに尊重して生きなければいけないんだ、ということを伝えたつもりです。日本にずっといるよりも、肌の色が違っても言語が違っても、考えることはみな大体一緒だということが、米国にいると実感しやすいですから。
若い医師にアドバイス「チャレンジする心を忘れないで」
――最後に留学を検討している若い医師に、改めてアドバイスをお願いします。
東梅 チャレンジする心を忘れずに、海外に出ていろいろなことに挑戦してほしいと思います。研究だけではありません。若い時期に異文化に触れることも大事です。留学することで、日本では経験できなかったことができたり、日本では見えなかったものが見えるようになったりします。
留学先は、自分で探す方法もありますが、私は先輩医師からの紹介でした。紹介で留学する利点は、紹介してくれる方を通じて、留学先のボスとの信頼関係が最初からある程度できていることだと思います。紹介で留学したいなら、積極的にいろいろな先生と交流を持って、「私は留学したい」「留学先を紹介してほしい」とアピールしておくことが大事です。そうすればチャンスは必ずやって来ます。
留学資金については、少なくとも1年分は自分で用意する場合が多いと思います。奨学金が獲得できるよう、論文をしっかり書いておいてください。もちろん良い雑誌に掲載されればいいのですが、それが難しくても、たくさん論文を書いていれば努力していることは伝わります。
基礎研究で留学するなら、家族と過ごす時間はしっかり取れると思います。日本人医師は、家族とゆっくり時間を過ごすことに慣れておらず、最初は戸惑うかもしれません。私も渡米後しばらくは戸惑いました(笑)。しかし助け合いながら異国で暮らすことで、家族との絆は強くなります。米国の場合は特に、諸々のことが子どもや家族を中心に回っているところがあるので、家族同士の交流を通じて新しい出会いがあったり、新しい経験ができたりすることも多いです。
私は、MIT(マサチューセッツ工科大学)で女性教授として活躍している山下由起子先生ご夫婦と、子ども同士が同級生ということもあり現在も交流が続いています。また、City of Hopeの骨髄移植部門責任者の中村亮太郎先生とも仲良くさせてもらっています。ですから可能であれば、家族みなで留学することをお勧めします。
米国で臨床検体を使ったエピジェネティクス研究を実施
2024.01.22
ボストン留学、人間に幅ができたと思えることが一番の成果
武井 裕史(たけい・ひろし)氏
2010年慶應義塾大学医学部卒業、北里研究所病院初期臨床研修医。2011年慶應義塾大学病院初期臨床研修医。2012年同内科専修医。2013年川崎市立川崎病院総合診療科専修医。2014年慶應義塾大学病院リウマチ・膠原病内科入局、慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程入学。2018年川崎市立川崎病院リウマチ膠原病・痛風センター副医長。2019年慶應義塾大学病院リウマチ・膠原病内科。2020年独立行政法人国立病院機構東京医療センター膠原病内科医員。2020年慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程修了・学位取得。2021年米国ハーバード大学医学部およびブリガム・アンド・ウィメンズ・ホスピタルのリサーチフェロー。2024年慶應義塾大学病院リウマチ・膠原病内科助教。