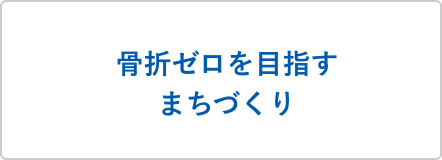信州大学医学部附属病院高度救命救急センターは、このほど国際航業と共同開発した「救急搬送時の遠隔作業支援システム」で、日本オープンイノベーション大賞の厚生労働大臣賞を受賞した。大学病院と企業による産学連携・医工連携のモデルケースで、救急患者の救命率向上と医療資源の有効活用を目的とする。今は実証実験を終えた段階だが、救急対応の質の向上を実現する取り組みとして期待を集めている。
施設情報
信州大学医学部附属病院 高度救命救急センター
信州大学医学部附属病院 高度救命救急センター
日本オープンイノベーション大賞は、我が国のオープンイノベーションをさらに推進するために、今後のロールモデルとなる先導的・独創的な取り組みを政府が表彰する制度で、内閣府が2018年にスタートした(https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/prize/)。内閣総理大臣賞をはじめ、各大臣賞や日本経済団体連合会会長賞、日本学術会議会長賞などが授与される。2021年の厚生労働大臣賞には、信州大学医学部附属病院高度救命救急センターと国際航業株式会社(東京都新宿区)が共同開発した「救急搬送時の遠隔作業支援システム」が選ばれた。
このシステムの実証実験は、日本学術振興会の科学研究費助成事業として行われてきたものだ。その先進性と有用性に着目した信州大学の学術研究・産学官連携推進機構が、同大学医学部附属病院高度救命救急センター長の今村浩氏に働きかけ、日本オープンイノベーション大賞の申請に至ったという。「大学病院で働く私たちは、産学連携のシステムや手続きなどについて不案内です。そうした事情を理解して、産学連携の橋渡しをしてくれた学術研究・産学官連携推進機構には感謝しています」と今村氏は語る。
救急救命士に医師がオンラインで指示
日本オープンイノベーション大賞の厚生労働大臣賞を受賞した「救急搬送時の遠隔作業支援システム」とは、どのようなものなのか。一言で言うと、救急現場で患者に対応する救急救命士と、受入病院の医師との間で画像情報をやり取りすることによって、救急医療の質の向上を図るシステムだ。
救急医療では、1分1秒でも早く治療介入することが、患者の救命や社会復帰につながる。その意味でドクターヘリやドクターカーの意義は大きいが、絶対数が限られており、全ての救急患者に対応できるわけではない。また、ドクターヘリは夜間に飛行できず、ドクターカーは全ての地域をカバーしているわけではないという限界もある。
そのため実際には、多くの場合、最初に患者に接する救急救命士の対応が鍵を握ることになる。近年、救急救命士が行える特定行為(医師の具体的な指示の下に行う医療行為)の範囲が徐々に拡大されており、救急現場で医師からの指示を受ける場面が増えている。この救急救命士の活動を適切かつ効率的なものとするのが、通信手段を用いて医師が指示を行う「オンライン・メディカル・コントロール」だ。
現在は主に携帯電話が利用されており、現場の救急救命士から患者の状況を聞いた医師が、必要な指示を行う形で進められている。しかし音声通話では、やり取りできる情報は限られたものとならざるを得ない。その情報量を飛躍的に拡大する試みとして、今村氏らの取り組みが今、注目を集めている。
画像で得られる情報量は圧倒的
「救急搬送時の遠隔作業支援システム」では、眼鏡型のウェアラブル端末「スマートヘッドセット」を装着した救急救命士の視野の画像と音声が、受入病院の医師にリアルタイムで送信される(図1)。視野の画像には、血圧や酸素飽和度などの生体情報も含まれる。また、信州大学では以前から12誘導心電図の伝送にも取り組んでおり、そのデータも同時に送られる。反対に、受入病院側から現場の救急救命士に対し、画像データを送ることも可能だ。
このシステムの導入により、患者の予後は確実に良くなると今村氏は言う。「やはり『百聞は一見にしかず』で、画像から得られる情報量は音声とは比べものになりません。例えば心筋梗塞の患者さんを受け入れる場合、救急車での初期対応の段階で診断がつくわけですから、処置までの時間が短縮されますし、搬送している間に病院側で緊急カテーテル手術の準備を進めることなども可能になります」。
また、全てのデータがリアルタイムで見られるので、まるで医師がその場にいるかのような指示もできるようになった。例えば「心電計の電極の位置をもっと上に」といった指示が可能になったほか、心電図の状態から搬送先の病院を変更した例もあったという。「送られてきた画像から、患者さんの状態が思ったよりも重篤と判断された場合には、搬送先を二次救急医療機関から三次救急医療機関へと変更することもあります」と今村氏。
さらに外傷では、医師が患者の皮膚の色を見ながら、救急救命士に圧迫の強度を細かく指示するようなケースもあるという。「病院側で受け取る情報量が圧倒的に増え、的確な指示ができるようになったこと。これが『救急搬送時の遠隔作業支援システム』の最大のメリットです。病院に搬送されてきたあとで患者さんに対応するときも、同システムによって20分前の状況を実際に見ていたのとそうでないのとでは、診療効率が大きく変わります」と今村氏は話す。
 図1 眼鏡型ウェアラブル端末「スマートヘッドセット」
図1 眼鏡型ウェアラブル端末「スマートヘッドセット」
実証実験に大きな手応え
松本広域消防局の協力を得て2020年10月から実施されてきた「救急搬送時の遠隔作業支援システム」の実証実験は、2021年7月の終了までに10件ほどの実績を積んできた。コロナ禍により、当初想定していた数よりは少なくなったが、今村氏は大きな手応えを感じている。
「やってみて1例でも予後が改善し、デメリットがなければいいわけですから、かなり良い感触を得ています。受入病院の評価は総じて好評で、地域の医師会の先生方からも大きな反響をいただきました」と今村氏。救急救命士からの反応については「参加した人からは『すごく良かった』という声を聞いている一方で、装着によって現場活動や観察に制限が生じたという意見もありました。普段は付けない装備を付けることになる救急救命士の負担は大きいはずなので、これから使い勝手などについて詳細なヒアリングを進め、装備の改良なども考えていきます」と語る。
実証実験という性格上、今回は患者の予後に影響が及びかねないクリティカルな症例は対象外にしたとのことだが、今村氏によれば、同システムで最もメリットが大きいのは心肺停止のケースだという。「胸骨圧迫や気管挿管の局面でこそ医師の指示が生きるのですが、今はコロナ対応で感染防護用のゴーグルを着用せざるを得ず、眼鏡型のウェアラブル端末まで付けてもらうのは難しい状況です」。本命の心肺停止例をめぐる同システムの活用は、今後の課題として引き継がれた格好だ。
また同システムは、救急現場と受入病院が双方向で画像情報をやり取りできる仕組みだが、救急現場からの画像情報が活用される一方で、受入病院からの画像情報が生かされる場面はあまりなかったという。「救急医療の現場は緊迫していますので、画像による指示を落ち着いて受けられるか難しいところもありますが、今後は現場から送られた画像を静止画にして、そこに具体的な指示を書き込むようなケースが出てくることを期待しています」と今村氏は言う。
通信環境の改善も課題の一つだ。やり取りするデータ量が多くなるだけに、実証実験でも、電波状態によって通信が途切れてしまうなどのトラブルが一部で発生したという。今村氏は「細かい画像の送受信には、今の通信環境は万全ではありません。5G通信が当たり前になれば、その点は改善するでしょうし、救急救命士が書く報告書の文字もくっきり読めるようになり、申し送りが不要になるなどして利便性がさらに高まるはずです」と話している。
 図2 画像情報を活用した「オンライン・メディカル・コントロール」の概要
図2 画像情報を活用した「オンライン・メディカル・コントロール」の概要 救急医療情報システムとも連携
信州大学医学部附属病院高度救命救急センターでは、2021年10月から「救急搬送時の遠隔作業支援システム」の実証実験を再開する。今回は行政が整備している救急医療情報システムと連携した形での運用を計画しているという。「救急現場と受入病院のやり取りが1対1だとそのメリットは限られますが、オンライン・メディカル・コントロールは幅広い情報共有が可能なので、地域全体に大きなインパクトを与えられます。地域における救急医療の質の向上や医療資源の有効活用に、このシステムを生かしていきたいと考えています」と今村氏は意気込む。
救急医療分野における産学連携のモデルケースが、長野県の救急医療をどのように変えていくのか。その動向から目が離せない。
 信州大学医学部附属病院高度救命救急センターのスタッフたち。(今村氏提供)
信州大学医学部附属病院高度救命救急センターのスタッフたち。(今村氏提供)ーーーーーーーーーーーーー
今村 浩 氏
1987年横浜市立大学医学部卒。虎の門病院内科、日本医科大学救命救急センターを経て、1993年信州大学医学部附属病院医員、2003年同大学医学部救急集中治療医学助教授、2014年より同大学医学部集中治療医学教授。信州大学医学部附属病院高度救命救急センター長を兼務。