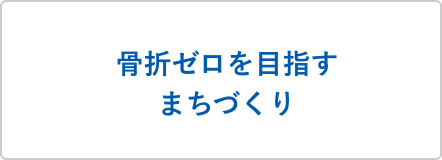新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)など、医療は近年、新興感染症の脅威にさらされてきた。名古屋大学医学部附属病院の中央感染制御部は、同病院において、これら感染症に対抗する最前線であり司令塔である。また同病院は、我が国の国立大学附属病院として唯一、アメリカの医療機能評価組織であるJCI(Joint Commission International)の認証を受けた医療機関でもある。医療の質と患者の安全を重視するJCIの評価に当たり、同病院の中央感染制御部は大きな役割を果たしたという。
施設情報
名古屋大学医学部附属病院 中央感染制御部(愛知県名古屋市)
名古屋大学医学部附属病院は2019年、国立大学病院として初めてJCIの認証を取得した。
名古屋大学医学部附属病院(名大病院)の中央感染制御部は、医師6名、看護師4名、臨床検査技師2名、薬剤師3名、事務員1名で構成されている。主な業務は、感染対策チームによる院内の感染管理および予防接種の推進、抗菌薬適正使用支援チームによる感染症診療支援など。医師は6名中4名が感染症専門医で、看護師は4名のうち感染管理認定看護師が1名(さらに1名が同資格試験を受験中)、感染症看護専門看護師が1名という感染症対策のスペシャリスト集団だ。
他科への感染対策・診療支援が主力業務
「中央感染制御部の大きな特徴の1つは、感染対策だけではなく、他科へのコンサルテーションや抗菌薬適正使用支援の業務にも力を入れていることです。他の診療科では患者一人ひとりに主治医がいますが、当部の医師は診療科横断的に患者を診ています」。中央感染制御部の部長で、名古屋大学大学院医学系研究科臨床感染統御学教授も務める八木哲也氏はこう語る。
八木氏はもともと呼吸器内科医を志していたが、呼吸器感染症の診療を経験するうちに感染症に関心を抱き、また薬剤耐性菌の研究を通じて、「感染症に診療と研究の両面からのめり込むようになった」(同氏)という経歴の持ち主だ。感染症診療の魅力は、その間口の広さだと話す。「感染症の病態は多彩ですが、診療のためにはまず各感染症に共通するロジックを理解する必要があります。それが分かれば、次に、患者の背景や罹患の要因が病態にどのように反映されているのか、そのバリエーションを学んでいくことになります」と言う。
感染症を専門にする医師は、結核やマラリア、エイズはもちろん、アフリカなどに特有の「顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases; NTD)」も守備範囲となる。NTDとは、患者数が少なく、地域性が高く、先進国からの関心が低い病気の総称である。リンパ系フィラリア症、シャーガス病、デング熱などが代表的なもので、主として発展途上国の貧困による劣悪な衛生環境が蔓延の原因とされる。これまで日本国内で遭遇することはまれであったが、気候の温暖化や人的交流の活発化を背景に、日本でも輸入感染のリスクが高まっている。実際、2014年に蚊が媒介したデング熱の国内感染が確認されたのは記憶に新しい。
国内で患者数が少ない感染症を学ぶには、1つの病院内では当然、限界がある。しかし名古屋地域には、様々な感染症を学ぶためのネットワークが確立している。例えば、エイズについては国立病院機構名古屋医療センターが多くの診療実績を有する一方、輸入感染症には名古屋市立大学東部医療センターが強みを持つ。結核となると結核病床40床を擁する国立病院機構東名古屋病院があり、海外渡航前のワクチン接種の多くは名鉄病院予防接種センターが受け持つ。名大病院の中央感染制御部に所属する医師は、これら特色のある医療機関と連携して経験を積める仕組みになっている。
「中央感染制御部からは、様々な感染症に強みを持つ他の病院に短期間、勉強に出向くことも可能で、幅広い経験を通して専門を深めていくことができます。このように地域の医療機関が分担して感染症の専門医を育成するシステムが確立している点を、若い先生方にもぜひアピールしていきたいですね」と八木氏は話す。 中央感染制御部のスタッフたち。前列中央が八木氏。
中央感染制御部のスタッフたち。前列中央が八木氏。
コロナ禍の襲来を予見した?JCIの審査
感染症診療のエキスパートであり、専門医の育成にも力を注ぐ八木氏が最近「勉強になった」と振り返るのが、名大病院がJCIによる認証を受けたことだ。「JCIの審査のために準備を重ねたのですが、大変な作業でした。ただ、その準備を通じて病院全体の機能における感染症対策の位置づけを整理できたことは大きな収穫でした」と言う。
JCIは米国の病院機能評価組織の国際部門として1994年に設立された非営利団体で、「医療の質」と「患者の安全」を国際的な基準によって評価する。JCIの認証を受けると病院が国際的な“お墨付き”を得たことになるので、海外の医療保険会社と提携しやすくなったり、医療ツーリズムの患者を獲得しやすくなるなどのメリットがある。現在、全世界で1066施設が、日本では30施設が認証を受けており、その中には4つの大学病院が含まれる。2019年に認証を受けた名大病院はそのうちの1つであり、国立大学の附属病院としては唯一の存在だ。
認証を受けるためには、国際患者安全目標、患者の評価とケア、感染の予防と管理、ガバナンスとリーダーシップなど、15領域265項目に及ぶ評価項目についての審査を受ける。海外からやって来た5人ほどの審査員が、数日をかけて院内をくまなく回り、審査に当たるのが通例だ。
この審査の際、八木氏は審査員から忘れられない質問を受けた。「空気感染する感染症に罹患した患者が病院に大挙して押し寄せたときの対応を準備しているか」という質問だった。審査が行われた2019年前半にはまだCOVID-19の流行が発生しておらず、八木氏は質問の意図を測りかねた。「何のことだろう。日本で一部、麻疹が流行したことを指摘しているのだろうか」。感染症の専門家である八木氏がそのとき、真っ先に思い浮かべたのが麻疹だった。
しかし、翌年には日本にもCOVID-19が本格上陸し、全国の医療現場を大混乱に陥れた。「ああ、このことか」。八木氏は合点がいった。パンデミックの襲来によって日本の医療機関はその対策に追われ、通常の診療を継続することが困難になった。JCIの審査員は、そんな状態になっても病院が機能を維持できるか、患者の安全を確保できるかを問うていたのだ。スペイン風邪以来、世界が経験していなかったような事態までを想定したJCIの審査の在り方は、八木氏に強い印象を残したという。
個々の症例に応じたきめ細かな抗菌薬適正使用支援
新型コロナウイルスと並んで医療機関の大きな脅威となっているのが、薬剤耐性(AMR)の広がりだ。病院で薬剤耐性菌が発生すると、感染対策で患者の負担も医療従事者の負担も大きくなる。多剤耐性菌の場合は、感染対策はより厳重になり、感染症の治療がより難しくなって、患者の生命予後にもかかわることになる。AMR対策を含む感染管理も、名大病院中央感染制御部の重要な役割だ。
AMR対策の一環として、名大病院では注意を要する薬剤の使用を届け出制にするとともに、その使用を管理している。八木氏は「緑膿菌とMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)への抗菌薬の使用時には届け出を義務づけています。届け出が必要な抗菌薬が使用されたときには、まず薬剤師が投与開始前の微生物検査がなされているか、経験的治療が患者さんの腎機能に合わせた適切な投与量となっているかを確認します。その後、投与4日目に医師が、微生物検査結果と照らし合わせて適切な確定的治療になっているかをチェックしています」と話す。
問題があると判断された場合は、主治医に連絡し、抗菌薬の種類や用量の変更や投与中止をアドバイスする。2017年以前は、問題ありとされた抗菌薬の使用が全体の20%を超えていたが、現在では十数%にまで低下している。「この値を10%以下にすることが当面の目標です」と八木氏は語る。
また、抗菌薬の適正使用の重要な指標であるDOT(使用日数)に基づくチェックも重視している。AMRが問題となる疾患の1つにカルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症があるが、カルバペネムの使用が10日を超える場合は必ず確認を入れるという。
ただし、10日を超えるカルバペネム使用例の全てに問題があるわけではない。小児がん拠点病院でもある名大病院では、小児の発熱性好中球減少症(FN)が多く、カルバペネムの連用が合理的であるケースもある。こうした個々の事情を考慮しながら、中央感染制御部では、きめの細かい抗菌薬の適正使用支援を行っている。「同時に、血液培養検査で陽性となった症例にも診療支援に入っており、また全ての診療科からも症例のコンサルテーションを受けています」と八木氏。
このような支援を行うときには、カルテからの情報収集、患者さんの診察、主治医とのコミュニケーションを特に重視している。「主治医と感染症医とがコミュニケーションを取りながら対応を決めることで、患者に適正な治療が行われるようになると双方が実感できます。大事なのは、こうした成功体験を積み重ねていくことです」と八木氏は指摘する。
そのきめ細かなコンサルテーションを実現する上で欠かせないのが、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師といったスタッフ間の情報共有だ。感染対策チーム(ICT)全体では14日に1回のミーティングを定期開催しているが、より小さい規模のICTのコアメンバーによる「コアミーティング」を週に1回、開いている。「情報共有に漏れを少なくし、問題を共有してその解決を促進するための場がコアミーティングです。各スタッフが問題点を持ち寄り討議することによって、どのような対策を取るのかをその場で決めているのが特徴です」と八木氏は語る。
 臨床検査室で若手医師や臨床検査技師とディスカッションする八木氏(右)。(同氏提供)
臨床検査室で若手医師や臨床検査技師とディスカッションする八木氏(右)。(同氏提供)感染管理の専門ジャーナルへの投稿も
中央感染制御部のチームは2021年9月、専門のジャーナルに過去5年間の同院の感染症と抗菌薬の使用状況を報告した(Morioka H, et al. Infect Prev Pract. 2021; 3(3): 100151)。それによると、手術に際して予防的に投与される抗菌薬の量は劇的に減少していたものの、手術以外で予防投与される抗菌薬の量は徐々に増えていることが明らかになったという。この結果を踏まえ、八木氏は「院内で発生する耐性菌や、その原因となる抗菌薬の使い方は、時間とともに変化していくものです。適切な感染管理を行うには、こうしたサーベランスを毎年、実施していくことが欠かせません」と話している。
------------------------------------------------------
八木 哲也(やぎ てつや)氏
1988年名古屋大学医学部卒業。名古屋第二赤十字病院、名古屋掖済会病院、
名古屋大学医学部附属病院を経て、1998年国立感染症研究所主任研究官。
1999〜2002年米国コロラド州立大学留学。国立療養所中部病院、国立長寿医療センターを経て、
2008年名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部准教授、
2012年同大大学院医学系研究科臨床感染統御学教授。