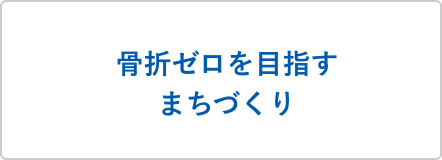長崎大学病院リウマチ・膠原病内科(第一内科)教授の川上純氏は、大学卒業と同時に同大病院の第一内科に入局。以来30年以上にわたり、同病院でリウマチ・膠原病領域の診療に当たってきた。2010年に主任教授に就任してからは、臨床にフィードバックできる研究の重要性を医局員に問いかける一方、研究活動で培った思考プロセスを臨床にも生かすよう後進を指導。2021年3月からは、離島や過疎地の医療機関と長崎大学病院をつなぐ関節リウマチ遠隔診療システムの実証実験にも取り組んでいる。
施設情報
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科先進予防医学共同専攻
長崎大学病院リウマチ・膠原病内科(第一内科)
長崎大学病院リウマチ・膠原病内科(第一内科)
医局データ
教授:川上 純 氏
リウマチ・膠原病内科スタッフ:22人
(内分泌・代謝内科スタッフ:20人、脳神経内科スタッフ13人)
リウマチ・膠原病内科外来患者数:約9600人(2020年)
川上純氏は、2010年から10年以上にわたって、長崎大学医学部内科学第一(第一内科)の主任教授を務めている。この期間に、川上氏の大学における肩書は、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座教授から、同研究科先進予防医学共同専攻教授へと変わった。
先進予防医学共同専攻は、長崎大学と千葉大学、金沢大学の3大学による共同大学院教育課程。個人や環境特性の網羅的な分析・評価を通じて実現する「精密医療」「個別化予防」という先進的な予防医学を実践する人材育成を目的に、先進予防医学共同専攻は2016年に開設された。「私たちの研究テーマである関節リウマチのような慢性疾患やpolygenic diseaseは、まさに遺伝的背景と環境要因の相互作用で発症する疾患なので、先進予防医学共同専攻の目的と合致しています」と川上氏は語る。
深く考察する習慣が臨床に生きる
川上氏は、1985年に長崎大学医学部を卒業して以来、研修医時代の1年と米国留学時の3年を除き、30年以上に及び長崎大学病院第一内科に籍を置く。「私たちが入局した時代は、大学卒業後3年目くらいに診療科や専門領域を決めるのが一般的でした。第一内科は複合内科なので、いったん入局してから専門領域を絞り込もうと入局当初は考えていました。ですが医師となって様々な症例を経験するうちに、その当時の入院患者さんの数は少なかったのですが、学生時代に教員の先生から話を聞いて関心を持っていたリウマチ性疾患に興味を惹かれ、この領域を自分の専門としました」と川上氏は話す。
リウマチ・膠原病内科の先輩医師から「若いうちに研究活動を経験しておいた方がよい」というアドバイスを受けたこともあり、研修医として勤務していた長崎原爆病院から大学に戻った後、川上氏は大学院で学位を取得し、その後、米国ハーバード大学ダナ・ファーバー癌研究所に留学した。こうした経験を通じ、研究活動が臨床にもたらす意義を実感している川上氏は、学生や若手医師に対して、学位研究の思考プロセスの重要性を伝えている。
「大学院で研究テーマを決めて、3〜4年かけ深く思考する習慣を身に付けることは、その後の臨床で必ず役に立ちます。特に、診療ガイドラインの適応が難しい症例に遭遇した場合などでは、深く考察する習慣が、最適な治療法を選択する際に有意義に働くはずです」と川上氏。これは、川上氏が掲げる医局のコンセプト「病気の成り立ちをよく考えて診療すること」にも通じる。
臨床に根差したクリニカル・クエスチョンの解決へ
令和3年度に大学勤務のリウマチ・膠原病内科のスタッフは、教員である医師が12人、大学院生・医員・修練医が10人。それぞれが「関節リウマチのトランスレーショナルリサーチ」、「関節リウマチの疫学研究」、「全身性エリテマトーデスのトランスレーショナル研究」、「自己炎症性疾患のトランスレーショナル研究」、「炎症性筋疾患のトランスレーショナル研究」などの研究活動を行っている。
現在、日本赤十字社長崎原爆病院、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター、社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院、地域医療機能推進機構諫早総合病院、独立行政法人国立病院機構長崎医療センター、独立行政法人国立病院機構嬉野医療センターなどに、リウマチ膠原病内科医師を派遣している。
長崎大学病院におけるリウマチ・膠原病の病床は約15~20床。病床数が比較的少ないのは外来診療が主体で、他の医療機関から紹介を受け治療を終えて紹介元に戻した患者を3カ月から1年の間隔で定期的に診療している。こうした外来患者数が外来日1日当たり約50人、月に800人以上に達する。
「患者さんの治療が、診療科として最も大切なことですが、大学講座としてはエビデンスを構築することも重要なので、どちらもしっかり取り組んでいかなければなりません」。こう語る川上氏は、臨床に根差したクリニカル・クエスチョンを解決することを重視している。そのため医局員には、治療によって患者さんがどのような経過をたどりアウトカムに至ったのかを見極めることを求めている。
「臨床に根差したクリニカル・クエスチョンを解決していくことは治療成績の向上につながるので、医局として力を入れています。リウマチ・膠原病領域で様々なリサーチを展開しているので、興味を持たれた方はぜひご連絡ください」と川上氏は医局の門戸を開いている。
3次元映像による遠隔診療システムの開発にも取り組む
また、長崎大学病院第一内科では、長崎大学医学部地域医療学講座、長崎大学離島・へき地医療学講座と連携し、2021年3月から、離島や過疎地の医療機関や自治体、ソフトウエア開発メーカーとも協働して、関節リウマチ遠隔診療システムの実証実験にも取り組んでいる。
これはMixed Reality技術やAI技術を取り込んだ最先端の試みでもある。
多くの離島や過疎地を抱え、高齢化が進む長崎県では、地域医療維持の重要性が増している。島原や平戸から長崎市内まで移動するには、片道2〜3時間を要する。また、離島からの移動には、船舶や航空機に頼らざるを得ない。多くの症例を経験し知識習得に結び付けるという医師のキャリア形成の側面のみならず、都市部にアクセスしにくいといった時間的・地理的要因は、医師が離島・僻地医療を敬遠する理由にもなっている。
こうした現状に対し、川上氏は「過疎地などへ医師を派遣する障壁が距離にあるということであれば、IoT(モノのインターネット)化とICT(情報通信技術)システムの拡充によって、対応は可能になると考えられます」と言う。「例えば、テレワークなどを支える通信技術がさらに進歩すれば、離島・僻地医療に携わる医師であっても、情報収集におけるハンデが解消されていくでしょう。また、IoT技術が医療機器にまで広がれば、遠隔医療においても診療や治療の高度化が実現できます。現在、我々が取り組んでいるMixed Realityという技術も、そこを目指しています」とも付け加える。
Mixed Reality(以下、MR)はデジタル映像の表現技術。生成したデジタル映像を見せるVirtual Reality(仮想現実、VR)や、現実の視界に2次元のデジタル映像を重ね合わせたAugmented Reality(拡張現実、AR)に対して、MRは現実世界の中に3次元情報から生成されたデジタル映像を違和感なく重ね合わせる技術である。
長崎大学、長崎県五島中央病院、長崎県、五島市と日本マイクロソフトの5者は連携協定を締結し、MR技術を活用して開発した長崎大学関節リウマチ遠隔医療システム「NURAS(Nagasaki University Rheumatoid Arthritis remote medical System、ニューラス)」の実証実験を進めている。五島市が川上氏の先進予防医学共同専攻のコホート研究の母集団であることもあり、実証実験の地に選ばれた。「五島は比較的大きな離島ですが、専門医が非常に少ない地域です。その解決にはICTとIoTによる遠隔医療しかないと思いました」と川上氏は語る。
NURASは、従来のテレビ電話あるいはウェブ会議システムを用いた遠隔医療に加えて、マイクロソフトの「Azure Kinect DK」を深度センサーとして患者の前に設置し、病変部位を立体的かつリアルタイムに、遠隔地にいる専門医が観察・評価できるシステムだ。専門医と実地臨床医、患者の会話や各種データは、厚生労働省、経済産業省、総務相が所管する「3省3ガイドライン」に準拠したプラットフォーム上でセキュアに処理される。
「大学病院にいる専門医はゴーグルを付けると、ホログラムとして現れる病変部位を様々な角度から観察することができるので、関節がどれくらい腫れているかもすぐに分かります。2次元画像しか確認できなかったオンラインのウェブ会議より精度の高い診察が可能になります」。こう語る川上氏は、現システムの機能拡張として、搭載済みの人工知能の活用を考えている。「診療中の会話を文字に起こして電子カルテに入力できると診療効率が上がりますね。さらに、医師が見落とした病変部位をAIが見つけ出したり、患者さんの表情を分析して、医師にはなかなか言い出さないことがないかを推定できると助かります」。
専門医だけでなく医師が少ない地域のハンデを逆手に取った、長崎大学病院第一内科が手がける遠隔診療システム。その動向からは目が離せない。
 長崎大学病院第一内科リウマチ・膠原病内科のスタッフの面々。20人を超える大所帯で、主要病院に医師を派遣している。
長崎大学病院第一内科リウマチ・膠原病内科のスタッフの面々。20人を超える大所帯で、主要病院に医師を派遣している。(川上氏提供)
-------------------------------------------------
川上 純 氏
1985年長崎大学医学部卒。長崎大学医学部附属病院第一内科入局以来、同内科助手、講師、准教授を経て、2010年より同内科教授。(川上氏提供)