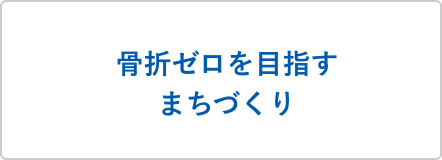2007年に愛知医科大学病院感染制御部として開設され、2013年に愛知医科大学病院感染症科となった部門の部長として診療の指揮を執る三鴨廣繁氏は、大学では医学部臨床感染症学講座の主任教授を務める。全国に先駆けて全ての新型コロナウイルス感染症患者に陰圧個室で対応するなど新たな試みに取り組む一方、大学の教授としては研究・教育・診療の各領域で感染症学のステータスアップに邁進している。
施設情報
愛知医科大学医学部臨床感染症学講座
愛知医科大学医学部臨床感染症学講座
医局データ
教授:三鴨 廣繁
医局員:常勤5名(教授:三鴨廣繁、准教授:森 伸晃、萩原真生(分子疫学・疾病制御学寄附講座 准教授)、講師:浅井信博、平井 潤);非常勤6名(客員教授:森 健、渡邉邦友、山下 誠、大曲貴夫、鎌田信彦、山岸由佳)、薬剤師1名(専従)、臨床検査技師10名(専従8名、再雇用1名、臨床感染症学講座研究員1名)、看護師4名(専従3名、時短勤務1名)、事務員3名
病床数:不定床(病院の方針で必要に応じて増減)
外来患者数:2,392人(初診407人、再診2,443人)(2021年度実績)
入院患者数:83人(2021年度実績)
感染症患者:870人(2,425件)(2021年度実績)
愛知医科大学医学部臨床感染症学講座の主任教授を務める三鴨廣繁氏は、2007年に愛知医科大学病院感染制御部として開設され、2013年に愛知医科大学病院感染症科となった部門の部長として診療の最前線に立っている。新型コロナウイルスが国内に広がり始めると、院内での感染拡大を防止し、職員の安全を守るために全ての感染患者について個室での対応を病院側に提案し、全国に先駆けて実現した。
その理由について、三鴨氏は次のように語る。「個室での患者受け入れを提案したのは、スタッフの安全を第一に考えたためです。多くの医療機関では、感染者がいるレッドゾーンと感染者が侵入しないグリーンゾーンなどに分けて、スタッフの動線を工夫していました。しかし、未知の感染症にスタッフが罹患することは絶対に避けなければと考えて、当院では陰圧設備を設置し、全ての感染者を陰圧個室に入れて、ウイルスの拡散を可能な限り押さえ込むことにしました」。
新型コロナウイルス感染が医療機関の人的リソースを圧迫
だが、他の医療機関の感染症医からは、「そこまでする必要はないのではないか」という声も聞こえてきたという。それでも三鴨氏は個室にこだわった。「患者さんの中にはマスクを着用できない人もいますから、ウイルスが漏れないようにするためには陰圧個室にする必要があります。おかげで当院では現在まで、院内での患者さんからスタッフへの二次感染を防ぐことができています」。さらに愛知医科大学病院では、全ての入院患者を対象に新型コロナウイルス感染の有無を判定するPCR検査を継続している。コストはかかるが、感染抑制を優先してのことだ。
ところが市中感染が増加すると、病院内での対策だけでは対応しきれなくなる。スタッフが家族から感染するなど、院外で感染する例が増えてくるからだ。「新型コロナウイルスの感染拡大第7波以降の特徴は、医療従事者も含めて誰もが感染し得るということです。スタッフがコロナに感染すると勤務できなくなるので、病院の機能が低下してしまいます。行政は病床使用率、重症者数、重症化率などの指標で対応を判断していますが、医療機関の人的リソースの減少を加味していません。このことはとても重要なのに、現実的には見過ごされているのが実情です」と三鴨氏は訴える。
入院は新型コロナウイルス感染症の中等症II以上という規定にも不都合があると三鴨氏は指摘する。「他の疾患で入院する患者さんの中には、入院時は新型コロナウイルスが陰性でも、入院後に感染が発覚する軽症の人がいます。そのような患者さんは転院先がないので、当院で入院治療予定の疾患と新型コロナウイルス感染症とに、同時に対応せざるを得ないのが現実です」。
加えて三鴨氏は、海外の状況を元にした市民の感染対策や、感染症分類変更の議論について次のように語る。「マスクを外して会食したり旅行している海外の様子を見て、うらやましくなったり、新型コロナウイルス感染症もインフルエンザと同等の扱いでよいのではと考えたくなることは理解できます。ですが、様々な病気やけがを治すためには医療リソースの確保が不可欠なので、国民の皆さんには今しばらく、医療現場を圧迫しないよう感染防止に最大限取り組んでほしいと思います」。
学会提言や診療ガイドラインに寄与する論文執筆を奨励
三鴨氏は、自身が理事長を務めてきた日本性感染症学会、日本嫌気性菌感染症学会をはじめ、様々な学会活動にも積極的に取り組み、医療関係者や一般向けの提言も行ってきた。「学会での提言作成には、さまざまな考え方を持つ方々と議論を重ねてコンセンサスを得ることが必要です。その元となるのが、論文として発表されたデータです。学術集会での講演以上に、文字化した論文が重要なのです」と言う。
そのため、三鴨氏が教授を務める臨床感染症学講座では、医局員やスタッフに積極的な論文投稿を促している。それは仮説に対するポジティブデータが得られたときに限らない。ネガティブデータであっても論文化することで、後世に残り議論の対象になり得ると三鴨氏は考えている。それらが診療ガイドラインの根拠にもつながっていく。
「教室から『PubMed』に掲載される英語論文を毎年20本前後発表しています。それだけでも十分誇りに感じていますが、ガイドラインに引用されれば医師冥利に尽きますね」と三鴨氏。臨床感染症学講座では、感染症全般の研究はもとより、「腸内細菌叢・腟内細菌叢と各種疾患との関わり」、「医療関連感染対策」、「不明熱の診断・治療」、「HIV感染症の診療」、「渡航者感染症診療」、「院内発症の感染症の診断・治療」など、多岐にわたる研究テーマに取り組んでいる。
 感染症科のカンファレンスの様子。画面奥の右側が三鴨氏。(三鴨氏提供)
感染症科のカンファレンスの様子。画面奥の右側が三鴨氏。(三鴨氏提供)
卒前教育では2年次から微生物学に触れ臨床応用を学ぶ
三鴨氏は、感染症科が設置される前、2007年に感染制御学の主任教授になった時から、卒前教育の充実に取り組み続けている。医学部の4年生に対して臨床感染症学の講義を34コマ担当し、感染症学を体系的に教えてきた。また、学習内容の定着率を上げるため、提示した症例について学生に考えさせ発表させるという双方向の教育システム「アクティブ・ラーニング」を積極的に取り入れている。臨床上の具体的なプロブレムを提示して、それについて学生と考えながら診療を進めていく「プロブレム・ベースド・ラーニング」という形式も導入した。
愛知医科大学病院に感染症科が設置されてからは、2年生を対象に基礎感染症学のコマを新設して、その講義も三鴨氏を含めた教室員が担当するようになった。その後、免疫学の講座と共同で微生物・基礎感染症学の講義に拡張・充実させて、基礎と臨床を融合させた8コマの講義を行っている。「2年生という早い時期に微生物学を学ばせ、その後に、臨床で微生物学がどのように応用されるかを細菌学、真菌学、ウイルス学を含めた総合的な感染症学・感染制御学として教えています」と三鴨氏は語る。
4年生の後期からは臨床実習「クリニカルクラークシップ」が始まる。クリニカルクラークシップにはAとBの2種類があり、Aでは学生全員が循環器内科や呼吸器内科、肝胆膵内科など様々な診療科を1週間単位で回る。その中には感染症科も含まれている。
クリニカルクラークシップBは、個々の学生が興味を持った、あるいは将来専攻したいと考える診療科を選択して1カ月ずつ、8カ月かけて回る。「クリニカルクラークシップBでも、感染症科は人気があります。マンツーマンで教える都合上、人数制限をしているため、クリニカルクラークシップ前までの学業成績が悪いと感染症科には来られないこともあります」と三鴨氏は話す。
感染症専門医の育成や活躍の場の拡大に意欲
卒後教育では、研修医を対象にした「モーニングカンファレンス」を開催している。その中で三鴨氏は、年に2回ほど感染症や感染制御の講義を担当する。そこで出会う研修医の中には、選択ローテーションで感染症科を経験した後、感染症科へ進むことを希望する例もあるという。そのような研修医に三鴨氏は、大学院への進学を勧めているという。また、「救命救急医学講座に入局しても感染症に興味を持っている医師の中には、講座教授の了解を得て、大学院では臨床感染症学を選択する例もあります」とも付け加える。
「専門医制度の2階部分のサブスペシャルティ領域に感染症専門医がありますが、その育成は日本感染症学会の目標でもあります。同時に、感染症学を専攻した医師が活躍する場を増やしていくことも課題です」。こう語る三鴨氏は、愛知県内における感染症診療の充実に意欲を見せる。「県内を見ても、感染症科がある病院は極めて少ないのが現状です。基幹病院に感染症科が設置されれば、医局から医師を派遣することで、地域の感染症診療をレベルアップさせることが可能になるでしょう」。
愛知医科大学の臨床感染症学講座からは、既に高知大学の臨床感染症学講座と和歌山県立医科大学の臨床感染制御学講座に、2人の教授を送り出している。「私立大学から国公立大学の教授を2人も出せたことは誇りです。旧六医大で感染症学のメッカとも言われる長崎大学には及びませんが、新設私大としてこれからも頑張っていきたいと思います」と三鴨氏は意気込む。
 臨床感染症学講座の医局風景。手前に写る大テーブルはディスカッションなどに使われる。(三鴨氏提供)
臨床感染症学講座の医局風景。手前に写る大テーブルはディスカッションなどに使われる。(三鴨氏提供)独立した「感染症科」の必要性を訴え続ける
医療機関が新たな診療科を開設する際には、患者数などから弾き出した採算性が大きなカギになる。だが感染症科は、季節ごとに患者数が変動したり、海外からの輸入感染症が影響したりするので、採算性が高いとは言えず、独立した診療科として開設される例は多くないのが実情だ。
そうした現状に対し、三鴨氏は独立した感染症科の必要性を訴え続けている。「医療機関に感染症専門医が必要な場面は、いろいろあります。1つは院内でのコンサルテーション。他科受診を依頼しなくても抗菌薬適正使用支援チーム(AST)のラウンドで、耐性菌に対する抗菌薬の使い方や抗真菌薬の処方期間などのアドバイスを受けることができます。今は入院時に診療報酬にAST加算が付くのですが、コンサルテーションするごとに感染症科の診療報酬が得られるようにしてもよいのではないかと思います」。
もちろん、三鴨氏はコンサルテーション業務だけに甘んじるつもりはない。「感染症科は、私どもの病院のように有床の診療科として、他科では担当できない感染症を治療していくことも必要です。感染症科を開設する病院が増えれば、大学医局でも感染症の専門医を増やすことが容易になるので、地域や愛知県全体の感染症対応力が増強され、新興感染症にも対応できるようになるでしょう」と言う。
一方、多くの医療機関では中央臨床検査部の下に感染検査室などが置かれているが、愛知医科大学病院では、微生物学検査を担当する部署が感染症科/感染制御部の直属になっている。「感染症の治療には原因となっている微生物の特定が必須ですが、当院の場合は中央臨床検査部を通さず検査を直接依頼できるので、迅速に対応できます。感染検査室・感染管理室のスタッフ8人(コロナでの特例雇用1名、臨床感染症学講座研究員としての雇用1名を含め合計10名)の人事権も私にあるので、彼らの専門性を高める方策を検討していくことも可能です」と三鴨氏。こうした体制は、全国の大学病院でも珍しいという。
 感染検査室。必要な検査を感染症科から直接オーダーできるために迅速な対応が可能だ。(三鴨氏提供)
感染検査室。必要な検査を感染症科から直接オーダーできるために迅速な対応が可能だ。(三鴨氏提供)コロナ禍を機会として感染症学のステータスアップを目指す
2020年に始まった新型コロナウイルス感染症の拡大は、感染症対策の重要性を改めて世に示すことになった。三鴨氏はこれを、感染症学のステータスアップにつなげたい考えだ。「コロナ禍はピンチではありますが、このピンチを感染症学をメジャーなものにするチャンスへと変えていかなければなりません。公衆衛生学的なアプローチをする先生、生物学的な基礎からのアプローチをする先生、純粋に臨床で患者さんを診る先生、それから統計的なアプローチをする先生と協力し合い、感染症に関わる全ての診療領域の先生とも連携しながら、感染症学のステータスアップを図っていきたいと考えています」。
------------------------------------------
三鴨 廣繁 (みかも ひろしげ) 氏
1983年名古屋大学文学部卒業。1989 年岐阜大学医学部卒業。岐阜大学医学部附属病院(産科婦人科)、Channing Laboratory, Harvard Medical School留学、岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科感染症治療学准教授、愛知医科大学大学院医学研究科感染制御学主任教授などを経て、2013年より愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学および愛知医科大学病院感染症科/感染制御部主任教授。